講演者インタビュー
中外製薬が実践する“全社を巻き込む”仕事と介護の両立支援~効果が見える施策設計のポイントとは~

株式会社チェンジウェーブグループ 変革ソリューション事業本部 ビジネスケアラー支援事業部 部長
中根 愛氏
本年4月に法改正があり、厚労省も実務対応が示されました。しかし現状では、自社の両立支援の実態を把握できておらず、悩んでいる企業が多く存在します。本講演では、仕事と介護の両立支援をDEI推進の一環として位置づける中外製薬をゲストにお迎え。管理職が両立支援の理解を深めることを起点に全社へ展開し、介護開始前から情報提供や自分ごととして両立準備の意識づけをどう推進してきたのか、具体的な成果もご紹介します。
―― 今回の貴社講演はどのような課題をお持ちの方向けの内容でしょうか?
本年4月に育児・介護休業法が改正され、さらに厚労省からは「従業員の就業継続を目的とした両立支援」を求める実務対応が示されました。
しかし現状では、自社の両立支援の実態を十分に把握できておらず、どの施策が効果的なのか、どこまで整備すべきか悩まれる企業のご担当者も少なくありません。
本講演では、多様な社員が、介護に直面しても安心して働き続けられる環境づくりに取り組んできた中外製薬の事例をご紹介します。社員への周知や学びの機会を通じて、介護前からの「両立の意識づけ」や主体的な準備を促す具体的な施策、その全体像をお話しいただきます。
法改正を機に、自社で実効性のある両立支援をどのように設計・推進すればよいかを模索されている人事・総務ご担当者の皆さまにとって、有益なヒントが得られる内容です。
―― 今回の講演の聞きどころ・注目すべきポイントをお聞かせください。
持続的な成長を支える「人的資本経営」が求められる中、社員がキャリアを継続しながら介護と仕事を両立できる環境整備は、ダイバーシティ推進の重要な柱です。しかし現場では、制度を整えるだけでは十分に機能せず、社員や管理職の意識改革や実効的な施策と運用の仕組みづくりが不可欠です。
本講演では、「仕事と介護の両立支援」に継続的に取り組み、実効性を高めてきた中外製薬の事例をご紹介します。同社では、施策全体の両立支援のポイントを押さえた設計に加え、社員が効果的に相談窓口を利用できる仕組みを構築し、管理職を巻き込みながら「仕事と介護を両立する」意識を醸成しています。さらに、社員への継続的な情報提供や相談体制の充実、組織内でのコミュニケーション支援を組み合わせることで、社員が早期から備える行動を促す環境を実現しています。
本講演の聴きどころは、単なる制度紹介にとどまらず、「自社では何ができるか」を具体的に考えられる実践的ヒントが得られることです。人材の活躍を後押しするDEI施策としての「仕事と介護の両立支援」のあり方を、多面的に学べる機会です。
―― 講演に向けての抱負や、参加される皆さまへのメッセージをお願いします。
仕事と介護の両立支援は、法改正対応にとどまらず、多様な人材が安心して働き続け、企業の持続的成長を支えるための重要なテーマです。本講演では、中外製薬の実践事例をもとに、介護が始まる前の社員にも「就業を継続して両立する」意識を浸透させてきたプロセスや、その効果をご紹介します。
継続的な取り組みによって「両立できる」と考え、行動する社員を増やしてきた事例は、多くの担当者の皆さまにとって参考になるのではないでしょうか。ぜひ自社の状況を思い描きながらご参加いただき、実効性ある両立支援策を推進するためのヒントを持ち帰っていただければ幸いです。
- 中根 愛氏(なかね まな)
- 株式会社チェンジウェーブグループ 変革ソリューション事業本部 ビジネスケアラー支援事業部 部長
- 2020年に旧株式会社リクシス(現:チェンジウェーブグループ)に参画、カスタマーサクセス部門の立ち上げ、2022年から現職。企業向けビジネスケアラー支援の責任者としてDEI部門や人事部門を中心に支援。企業の目標・課題に寄り添い、課題解決、施策運用~効果測定まで一気通貫でサポートを行っている。
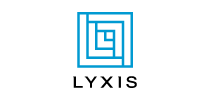
「日本の人事部」「HRカンファレンス」「HRアワード」は、すべて株式会社HRビジョンの登録商標です。
当社はプライバシーマーク取得事業者です。類似のサービスやイベントとの混同にご注意ください。