講演者インタビュー
実態把握から始める「仕事と介護の両立支援」
~制度づくりで終わらせない効果的な両立施策とは~

独立行政法人労働政策研究・研修機構 副統括研究員
池田 心豪氏
育児・介護休業法の法改正もあり介護支援施策を検討している企業が増えている中で、自社の施策が本当に効果的か不安に思う方も多いのではないでしょうか。施策の検討にあたってはまず自社の実態を正確に把握することが重要です。本講演では、労働政策研究・研修機構にて仕事と家庭の両立を研究されている池田心豪氏とともに、仕事と介護の両立施策において実態把握から始めるからこそ得られる効果や具体的な進め方を解説します。
―― 今回の貴社講演はどのような課題をお持ちの方向けの内容でしょうか?
高齢化社会の加速により、今後ますますビジネスケアラーが増えていくなか、2025年4月には法改正もあり、企業において「仕事と介護の両立施策」への重要性はますます高まっています。一方で人事の方からは、「制度は整えているが利用されていない」という声や、「制度を整える以外にどういった施策から始めていくのが効果的かわからない」という声も聞かれます。
本講演では、両立支援施策を行っていくうえで何から取り組めば良いのかを検討中の方や、施策は実施しているが今ひとつ効果を感じられないとお悩みの方に向けて、両立支援の第一歩として、社内の実態把握から始めることの重要性についてお話しします。
―― 今回の講演の聞きどころ・注目すべきポイントをお聞かせください。
介護と仕事の両立施策において、なぜ実態把握から始めると良いのかを具体的に解説していきます。実態を把握することで、施策の内容や効果がどのように変わるのか、実践することのメリットやイメージがわくような形でお伝えします。
介護問題は見えにくいため後回しにされがちですが、適切な対策を講じないと介護者の離職や業務パフォーマンス低下が生じ、企業全体の生産性低下につながる恐れがあります。この機会に、実態把握の重要性を理解し、施策の第一歩として始めることで、自社にとっての適切な施策を効率的・効果的に実施できると考えています。
―― 講演に向けての抱負や、参加される皆さまへのメッセージをお願いします。
2025年4月の法改正により、仕事と介護の両立施策の必然性が高まっています。今回の法改正は企業が「従業員をより大切にする組織」へと進化する絶好の機会です。法改正を「義務」として受け止めるのではなく、「きっかけ」として捉え、社内の風土や価値観を見直すタイミングにしていただけたらと考えています。
制度の整備だけでなく、社員が声を上げやすい文化、そしてチームで支え合える職場づくりへ。表面的な対応ではなく、根本からの改革に向き合うことが求められています。社員の人生に寄り添う企業こそが、これからの時代に選ばれる存在となるはずです。皆さまに役立つ情報をお届けしますので、ぜひご参加ください。
- 池田 心豪氏(いけだ しんごう)
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構 副統括研究員
- 厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」「『転勤に関する雇用管理のポイント(仮称)』策定に向けた研究会」委員。 ほかに「両立支援ベストプラクティス普及事業」「仕事と介護の両立支援事業」厚生労働省委託事業の委員を数多く務める。
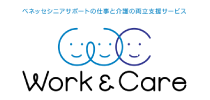
「日本の人事部」「HRカンファレンス」「HRアワード」は、すべて株式会社HRビジョンの登録商標です。
当社はプライバシーマーク取得事業者です。類似のサービスやイベントとの混同にご注意ください。