従業員エンゲージメントの未来を拓く、
VoE(従業員の声)とフィードバック
山本 勲氏(慶應義塾大学 商学部 教授)
三村 真宗氏(株式会社U-ZERO 代表取締役CEO兼CPO)
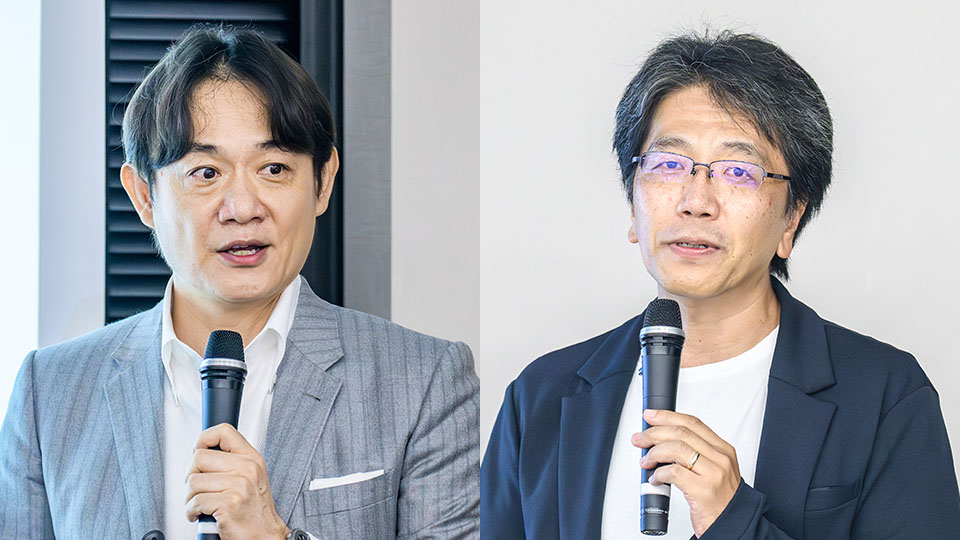
従業員の組織への愛着やコミットメントを示す「従業員エンゲージメント」を向上させるために、エンゲージメントサーベイに注力する企業が増えている。しかし従業員が多い大企業ではサーベイの集計や分析に時間がかかり、経営施策や課題の改善まで手が回っていないのが実状だ。中小企業では、従業員エンゲージメントの測定すらできていないことも多い。その背景には価値観の多様化により、何を改善すれば従業員エンゲージメントが向上するのかが見えにくい状況がある。どうすればこの問題を解決できるのだろうか。
8月1日に開催された「HRカンファレンス2025-夏-」では、慶應義塾大学教授の山本勲氏、組織エンゲージメント改革のリーディングカンパニーである株式会社U-ZEROのCEO兼CPOの三村真宗氏による現状分析・問題提起を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちがエンゲージメントについて語り合った。
【解説】
エンゲージメントとは|人事辞典『HRペディア』

- 山本 勲氏
- 慶應義塾大学 商学部 教授

- 三村 真宗氏
- 株式会社U-ZERO 代表取締役CEO兼CPO
山本氏による問題提起:エンゲージメントをどのように向上させるのか
労働経済学を専門とする山本氏は、エンゲージメントについて、「学術から普及した『ワークエンゲージメント』と、ビジネスの場で注目されている『従業員エンゲージメント』があります」と解説した。
「ワークエンゲージメント」は、従業員の仕事に対するポジティブな心理状態を指す。仕事に対してどれだけ熱意を持って取り組めているか、没頭できるかといった視点で計測することができる。これに対して「従業員エンゲージメント」は、企業と働き手とがどれだけ良好な関係を結べているかが指標となる。従業員が組織の理念に共感できるか、自社をどれだけ他人に薦められるかといった点がポイントとなる。
「これまでは、金銭的に豊かになることが従業員にとっての幸福でした。しかし近年は非金銭的指標であるやりがいや成長、ワークライフバランス、安全・安心を求めるなど、個人の幸福に対する価値観は多様化しています。成熟した社会で人々がウェルビーイングや持続可能な社会に注目するようになり、二つのエンゲージメントも世界的に注目を集めています。しかし、日本は他国と比較して、ワークエンゲージメントと従業員エンゲージメントのいずれもスコアが低いのが実状です」
従来の経済学では、労働はウェルビーイングと「トレードオフ」の関係にあり、両立は困難とされてきた。企業のCSRや福利厚生に該当するウェルビーイングを充実させれば、労働によって生じる企業業績に影響が出るためだ。このトレードオフ関係を「両立」に転換させるために、働くことそのものから幸福を感じられないかと注目されているのが「エンゲージメント」なのである。
日経スマートワーク経営研究会の調査によれば、ワークエンゲージメントと企業の業績指標には正の相関関係がある。ワークエンゲージメントが中央値以上の企業は、ワークエンゲージメントが中央値よりも小さい企業と比較して利益率が高くなっている。同様に従業員エンゲージメントの平均値が高くなると企業の利益率は上昇するが、従業員間でのエンゲージメントにばらつき(標準偏差)が大きいと利益率は減少するという結果がある。
「従業員の属性別に、30代以下、男性、長時間労働者、短時間睡眠者の従業員エンゲージメントが改善すると、利益率が上昇する傾向が出ています。会社や仕事がもともと好きな従業員のエンゲージメントをさらに高くするアプローチは取り組みやすいでしょう。しかし、仕事のモチベーションの低い人、会社の考えに共感できない従業員のエンゲージメントを高めることは、とても難しくなっています」
さらに山本氏は、経済産業研究所での共同研究を紹介した。大手小売業一社が毎年実施する従業員満足度調査にワークエンゲージメントの設問を追加し、従業員のワークエンゲージメントが高い売場ほど売上高が高いかを検証したものだ。ポイントは、ワークエンゲージメントの平均だけでなく「ばらつき」に注目した点だ。
従業員のワークエンゲージメントの平均が高い売場では、予測対比での売上高が高くなる傾向が見られた。しかし従業員のワークエンゲージメントの平均が高くても、従業員のワークエンゲージメントのばらつきが大きい売場では、生産性が低下する傾向も同時に見られた。仕事のモチベーションが高い社員と低い社員が混在する職場では、チームワークの悪化が生じて生産性に影響が出ている可能性が高い。つまり、生産性を向上させるためには職場の従業員全員がいきいきと働くことが求められるのだ。
では、ワークエンゲージメントを向上させるにはどうしたらいいのか。山本氏は、厚生労働省の『労働経済白書』令和元年版に掲載された『仕事の要求度・資源(JD-R)モデル』について解説した。
「JD-Rモデルによれば、仕事の裁量性や正当な評価といった『仕事の資源』と、自己効力感や楽観性といった『個人の資源』に対して、仕事量や精神的・肉体的負担など『仕事の要求度』が加わることで『ワークエンゲージメント』が発生するとしています。仕事の要求度が高ければワークエンゲージメントは低下しますが、仕事や個人の資源を増やすことができれば、パフォーマンスの向上などポジティブな成果を出すことができると考えられています」
個人の資源や仕事の要求度をコントロールすることは難しいため、ワークエンゲージメントを高めるには仕事の資源を増加させることが重要だと考えられる。仕事の資源を増加させる一例としては、上司のフィードバックや成長の機会を与えるなどの「人材マネジメント」、勤務間インターバル制度やテレワークの推進など「人材関連施策の導入・実施」、AIの活用など「テクノロジーの活用」、価値観や国籍、性別などの多様性を尊重する「DE&Iの浸透」と、さまざまな要因が考えられる。エンゲージメントを向上させるためには、組織がこれらを活用・整備していくことが重要だと山本氏は提言した。

参加者との質疑応答
ジョンソン・エンド・ジョンソン 西川氏:組織間のエンゲージメントにばらつきが大きいと業績にも影響するという指摘は大変勉強になりました。エンゲージメントを底上げするためにはどうしたらいいですか。例えば当社には社歴によってエンゲージメントサーベイのスコアにばらつきが見られるという課題がありますが、特定の属性のエンゲージメントを向上させる施策などの研究はあるのでしょうか。
山本氏:現在は価値観が多様化しているので、これをやればエンゲージメントが必ず向上するという特効薬はありません。ただ、前回よりスコアが下がった人は何か課題を抱えていることは事実なので、面談などで理由を深掘りし、解決策を見いだすとよいのではないでしょうか。逆に、エンゲージメントが下がっていないなら、うまくいっている証拠になります。いずれにしても、企業が従業員のエンゲージメントの状態を理解していることが大事だと思います。
三村氏による事例紹介:コンカーでのエンゲージメント改革事例
アイスブレイクとして各グループで自己紹介が行われた後、三村氏は前職でのコンカーのエンゲージメント改革事例について語った。コンカーは経費管理をクラウド上で行うサービスを展開する企業で、三村氏が社長在籍時に『Great Place to Work(働きがいのある会社)』ランキングにて史上初の7年連続首位を獲得した。ただし2011年10月社長着任時に調査したら、エンゲージメントが0%でもおかしくないような状況だったと、三村氏は振り返る。
「外資系企業の日本法人は、業績が全てです。私も数字を追い求めた結果、社内は分断されてしまいました。そこで2013年1月に全社員合宿を行い、5年後に『米国外で業績ナンバーワンの国になる』『日本のIT企業で最も働きがいのある企業になる』という二つの目標を立てました」
三村氏は、「沈黙と分断」から「対話と信頼」の文化への転換を目指し、二つの改革を行った。一つは、経営者が従業員の声(VoE:Voice of Employee)に耳を傾ける「タテの改革」だ。「経営者に自分の声が届く」という従業員の安心感を育て、自身の発言が組織の変化につながると実感させた。
もう一つは、フィードバック文化を醸成する『ヨコの改革』だ。従業員間で良いことも悪いことも伝え合うことで、本音の対話やお互いを尊重し合う関係性などを実現した。この二つの改革を推し進めることで職場には心理的安全性がもたらされ、結果として従業員の働きがい・エンゲージメントは向上し、業績も向上した。
「働きがいのある会社ランキングでは、7年連続1位という国内最長記録を達成しました。コンカー退任時には、国内時価総額トップ100企業の7割にシステムを導入。コンカーの暗黙知を、他社にも活用できるように仕組み化することにしました」
三村氏は、従業員エンゲージメントは正解がないからこそ「型」が活用できると語る。働きやすい職場は、人事制度や福利厚生を見直せば実現できる。しかし仕事のやりがいは、個人によって異なるため正解が分かりにくい。現在のエンゲージメント改革ではサーベイが中心となっており、肝心の戦略や改善に時間を割くことができないという課題もある。この難問を解決し、全ての人が幸せで働きがいのある未来を実現するために、U-ZEROを創業したと締めくくった。
参加者との質疑応答
質疑応答では、2社の参加者が三村氏に質問した。冒頭の質問で挙がった「VoEを活用している代表的な企業名」では富士通が例として挙がり、同社CHROの平松浩樹氏が約3000人のVoEを聞く取り組みを行ったことが三村氏により語られた。
明治 山口氏:ヨコの改革のフィードバック文化には、上司から部下への1on1などが該当するかと思いますが、同僚同士や部下から上司など、ナナメのフィードバックも活用できますか。
三村氏:どんどんやるべきです。私はマッキンゼー勤務時代にフィードバックの重要性を学びましたが、下から上、横などとにかくメンバー同士で高め合うことが根付いていました。
三村氏による解説:「エンゲージメント共創経営」は何を解決するのか
従業員エンゲージメント改革の型である「エンゲージメント共創経営」は、具体的に何を解決するのか。三村氏は、「従業員エンゲージメントの向上が、業績に直結する」と提言する。
「企業に売上をもたらすのは従業員です。従業員が会社にコミットしていなければ、離職率の高さやモチベーションの低下につながり、企業の生産性が落ちます。従業員定着率や仕事のモチベーションといった内部要因だけでなく、顧客へのサービス品質やロイヤルティなど外部要因にも大きく影響します」
ギャラップ社のメタ分析でも、従業員エンゲージメントが高い企業は、低い企業と比べて売上高、利益率、生産性、顧客満足度がプラス20%程度向上している。逆に休職率、離職率といったネガティブ要因はマイナスになっている。
しかし、エンゲージメントサーベイのスコアで表出する課題は氷山の一角に過ぎない。最も大切なのは、スコアに出てこないVoEである。エンゲージメントサーベイで自由記述の欄に書かれたコメントまで対応する企業は少ないが、実際にはそこに大きな課題が隠れていることは少なくない。
これまではVoEを集めるためには、忙しい従業員にフォームを回答してもらう必要や、人事部での集計の手間、共有するための資料作成など、多くの労力が割かれていた。だがクラウドとAIを活用すれば、集計の自動化や高度な分析も可能となる。

三村氏は、VoEに向き合うためには「コンストラクティブフィードバック」が有効に機能すると解説する。コンサルタントのようにAIが一人ひとりの従業員の声を掘り下げていくことで、簡素な回答ではなく課題の背景や従業員の考える解決策まですくい上げることが可能となる。海外拠点や外国籍従業員のVoEのヒアリングも可能だ。
「『人手不足』という自由記述だけでは現場の状況が分かりませんが、AIに回答を深掘りしてもらえば『現在は業務委託を活用しているが、管理にリソースが割かれている』など、詳しい実状が見えてきます。AIを活用すれば、課題を整理して優先順位を付けることも容易にできます」
集計したVoEを改善へとつなげるために必要となるのが「エンゲージメントサーベイ」だ。従来はVoEの結果分析は担当者の能力に依存していたが、U-ZEROのエンゲージメントサーベイではAIによって集計したVoEを組織、ヒートマップ、ランキングの三つの要素で分析できるのが特徴だ。部門や人物別にアラートも出せるので、対応すべき課題が可視化される仕組みとなっている。
「モニタリング」機能も組織改革に役立つ。チームシナジーモニタリングでは、A部門とB部門との仕事のしやすさや相性を計測することで、部門間のやり取りにトラブルが生じていないかを数値で把握できる。コンプライアンスモニタリングでは、VoEスコアの計測によってハラスメントやコンプライアンスの予兆を検知し、想起介入・対処を可能とする。ストレスマネジメントに活用し、うつ病や過労の予防につなげることもできる。
山本氏と三村氏による対談
続いて、山本氏と三村氏のエンゲージメントについての対談が行われた。
三村氏:U-ZEROで提唱する「エンゲージメント共創経営」という型は、困っている企業にとって有効だと思われますか。
山本氏:かなり有効だと思います。私が解説したJD-Rモデルでも、ワークエンゲージメントを高める資源を特定するのは難易度が高いとされています。VoEを活用してどの資源が不足しているかという課題を可視化できるのは、学術的にも有効だと考えられます。
三村氏:時間をかければexcel集計も可能ではありますが、AIを活用すれば富士通のような大企業でもできるようになりますからね。
山本氏:大企業はモニタリングだけでも大変です。逆にエンゲージメントに関心はあるけれど、どうしたらいいかよく分からないという中小企業でも、自動化は助けになるのでは。
お話を聞いていると、U-ZEROの提供するサービスは会社の細部までコンサルタントが常駐しているような印象を受けたのですが、まずはエンゲージメントから取り組んでいくということですか。
三村氏:経営に対する課題や仕事の危機意識に経営が一つひとつ向き合い改善していく過程で、間接的にエンゲージメントが向上すると考えています。
山本氏:AIのヒアリングでは、企業には関係のないプライベートな悩みも拾うのでしょうか。
三村氏:拾いません。「VoEを聞くと全ての悩みが噴出して『パンドラの箱』になるのでは?」と恐れる経営者もいるのですが、入口と出口設計を行えばいいのです。入口として、エンゲージメントサーベイを実施する目的を明確にして従業員にオープンクエスチョンを行えば、視座の高いVoEが集まります。意見を出しても改善がなされなければ現場は白けてしまうので、経営陣が現場の困り感にしっかり向き合う姿勢は求められます。
出口戦略では、集めたVoEをどう活用するかを従業員に開示します。VoEには現場の声が詰まっているので、具体的な施策が幾つも思い浮かぶはずです。例えばエンゲージメントサーベイの1ヵ月後に調査結果の報告とそこから生まれた具体的な施策を伝えれば、従業員からの信頼を得ることができます。
山本氏:なるほど。入口と出口戦略をしっかり行えば、サーベイだけで形骸化せずに中身のある施策を作ることができますね。
三村氏:全社員ではなく、子育て中の従業員など特定の属性にのみインタビューを行うなど、汎用性のある活用もできます。
ディスカッション1:VoEの現状と目指すべき理想像
続いて、参加者によるグループディスカッションが行われた。参加者には、自社のVoEの現状と経営層のエンゲージメントへの関心の高さ、自社が目指す理想像とそのために出来る施策というテーマが与えられた。参加者は五つのグループに分かれて話し合い、ディスカッション後は、二つのグループの代表者がディスカッション内容を発表。山本氏と三村氏がコメントした。

Cグループ
ボードルア 岡氏:三村さんの講演を聞いて、コンプライアンスの問題について早期に対策できるのが良いと思いました。当社はグループ全体で3000人なのですが、AIではなく人力で3ヵ月に1回サーベイを行っています。かなり大変ですが、離職率が下がるなど一定の効果は出ています。一元管理や打ち手が見えやすいのは非常に便利なので、ぜひ自社でも活用を検討したいと思いました。

Bグループ
大塚倉庫 島津氏:「入口と出口戦略の設計が大事」という点に共感しました。当社では、人事が全従業員の面談を行っています。倉庫の現場からは作業用具の好みなど本題と外れた話題も混在しやすいので、入口の質問内容を整理する大切さを改めて感じました。出口戦略でも、経営陣にVoEを伝えてどんなアクションを起こすのかを決める重要性を学びました。

山本氏:これまで人海戦術でやっていたことを、U-ZEROのサービスなどテクノロジーにより省力化できるのは、大きなメリットです。働き方改革の前後での調査結果では、管理職の労働時間が増えていることが明らかになっています。エンゲージメントの重要性や人的資本経営の推進によって管理業務のタスクは増えているので、負担軽減につながるサービスの活用も一案です。
三村氏による解説:フィードバックの効用と良好な関係性の築き方
グループディスカッションの内容を踏まえて、三村氏は、VoEをいかに経営層に届けるかという点も重要だと強調した。また、ディスカッション2のテーマである「フィードバック」の前段として、コンカー時代のフィードバック文化の有用性について語った。日本は空気を読むハイコンテクスト文化だが、良いことも悪いことも伝え合うことで成長やエンゲージメント向上につながると強調する。
「過去に私は、『ペン先を相手に向けない方がいいですよ』と部下から指摘を受けたことがあります。何気ない一言ですが、指摘してくれたことで私自身の成長にもつながりましたし、相手への感謝と信頼が生まれました」
また普段からポジティブフィードバックを行い、伝え手と受け手の間で良好な関係性を築くことも大切だ。三村氏曰く、「理想はネガティブ1、ポジティブ9」。経営層だけでなく、管理職や現場など全方向でフィードバック文化を醸成していくべきだと語った。

ディスカッション2:フィードバックの現状と取り組み
ディスカッション2では、自社におけるフィードバックの現状と理想を実現するための施策が各グループにて話し合われた。ディスカッション終了後は二つのグループの代表者による発表が行われ、山本氏がコメントした。
Aグループ
ヤマシタ 菅原氏:当社事業の一つに、在宅介護事業があります。チームの生産性を高めるためにフィードバックを重視しています。結果として、3年間で売上は100億円増加、昨年は平均年成長率を12%、従業員の給与は11%アップすることができました。要因としては、上司とメンバーの対話で「傾聴姿勢がとれ、耳の痛いフィードバックがある中で、相手が笑顔になっている」場合、生産性が高いことをAI分析で突き止めました。
3年前からリーダー・所長への「傾聴、Will/Can/Must、フィードバック」の研修を行い、実際の1on1に対して、AIと人事がフィードバックする取り組みをしています。人事制度でも、成長支援などのスキル発揮をスキルポイントで加算する仕組みを導入し、給与体系に組み込んだ結果、お客様への訪問件数やチーム内でのコミュニケーション量が増加しました。フィードバック文化の醸成は、生産性向上の一つの指標になってくると思います。

山本氏:フィードバックが行われている部署では、エンゲージメントのばらつきも小さくなっています。フィードバックをすることでお互いの理解が深まるので、エンゲージメントの差も収束していくのだと思います。
全体総括
最後に、三村氏がエンゲージメント共創経営の実現に向けて全体総括を行った。非財務データは重要とされているものの、計測が難しい。そのためU-ZEROのサービスでは、ダッシュボードにてエンゲージメントのインパクトや価値を可視化することに注力したと開発背景を語った。
「退職者の人数や各部署での従業員のストレス状況を経営陣が把握すれば、会社の健康度を測ることができます。自社のどこにひずみが出ているかを理解し、改善していくことが大切です」
本セッションのまとめ
| 山本氏による問題提議 |
|
|---|---|
| 三村氏による問題提議 |
|
| ディスカッション |
|
|
|
当日知見をご共有くださった皆さま
※所属や役職は「HRカンファレンス2025-夏-」開催時のものです。
有識者・プロフェッショナル
-
山本 勲氏
慶應義塾大学 商学部 教授 -
三村 真宗氏
株式会社U-ZERO 代表取締役CEO兼CPO
ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)
- (株)ARCALIS
- (株)INPEX
- SMBC日興証券(株)
- 大塚倉庫(株)
- (株)KOKUSAI ELECTRIC
- (株)COSPAウエルネス
- ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)
- 住友商事グローバルメタルズ(株)
- 都築電気(株)
- 日鉄鉱業(株)
- 日本キヤリア(株)
- ノバセル(株)
- パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)
- (株)富士通ゼネラル
- フジテック(株)
- ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
- (株)ボードルア
- 三菱地所ホテルズ&リゾーツ(株)
- (株)明治
- (株)ヤマシタ
- 横浜丸中ホールディングス(株)
- (株)菱友システムズ
U-ZEROは「すべての人が幸せで“働きがい”のある未来へ」を掲げ、世界従業員エンゲージメント調査での日本のエンゲージメントを昨年の6%から2030年に10%、将来的に世界平均の23%への引き上げを目指すスタートアップです。経営と従業員が対話を重ね、価値を共創する「エンゲージメント共創経営」実現のため、AIクラウド、コンサル、研修などの人的サービスの3事業で日本企業のエンゲージメント改革を後押します。





