人材ポートフォリオの“作り方”と“動かし方”
~その本質を問い、根本から考え直す~
守島 基博氏(学習院大学 経済学部 経営学科 教授 / 一橋大学 名誉教授)
冨樫 智昭氏(株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 エグゼクティブディレクター)
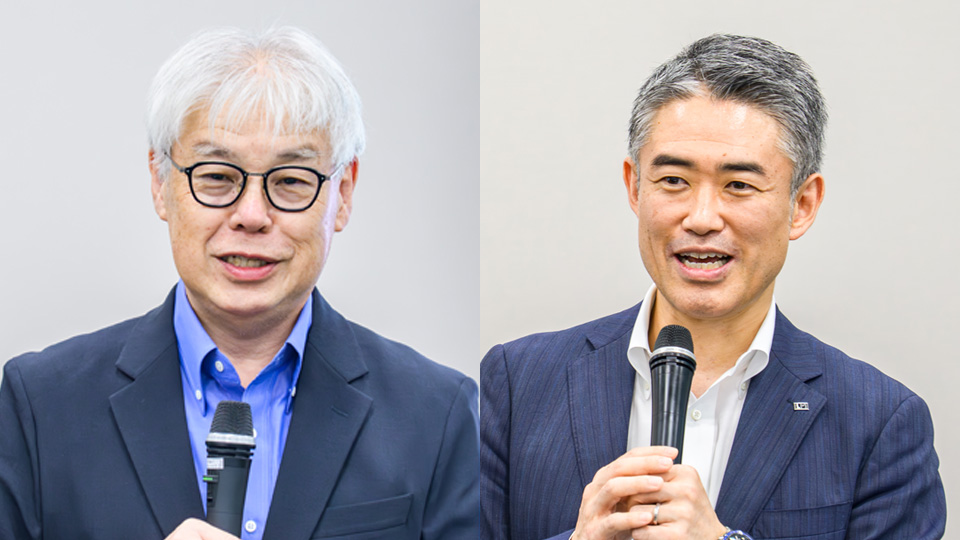
「人材ポートフォリオ」は、個々の人材の最適化ではなく、企業の戦略実現のために、どのような人材の「組み合わせ」が必要かを考えることから始まる。人材を期待される成果に基づいて分類し、その役割や雇用形態、処遇を設計していくアプローチである。当然、戦略が変わればポートフォリオも柔軟に変える必要がある。しかし、実際はこうした人材ポートフォリオの基本を認識し、実行に移すことは容易ではない。企業は人材ポートフォリオをどう作り、どのように運用していけばいいのだろうか。
8月1日に開催された「HRカンファレンス2025-夏-」では、学習院大学教授の守島基博氏、世界初の“モチベーション”コンサルティング会社である、株式会社リンクアンドモチベーションの冨樫智昭氏による現状分析・問題提起を受け、日本を代表する企業の人事リーダーたちが語り合った。
【解説】
人材ポートフォリオとは|人事辞典『HRペディア』

- 守島 基博氏
- 学習院大学 経済学部 経営学科 教授 / 一橋大学 名誉教授

- 冨樫 智昭氏
- 株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 エグゼクティブディレクター
守島氏による問題提起1:人材ポートフォリオは戦略人事を実行する方法の一つ
守島氏は、人材ポートフォリオの解説に入る前に、「戦略人事」について解説した。
「戦略人事とは、企業の戦略目標・経営目標の実現を目指した、人材マネジメントのこと。シンプルに言えば、『経営に資する人事』です。事業戦略や経営戦略を出発点とし、戦略目標の実現に不可欠な人材要件を定義した上で、その要件にフィットする人材を確保することで、初めて企業の目的が実現できます」
ここで守島氏は、戦略人事を達成するためには二つの重要なポイントがあると説明した。
「一つ目は、企業戦略が時代に合わせて常に変化している点です。重要なのは、戦略が変わるスピードのほうが人材を調達するスピードより明らかに速いこと。企業戦略に人材をフィットさせることが困難なのは、このスピードの差に起因すると言えるでしょう。
二つ目は、人材面でも、スキルや能力といった『ハード面』だけでなく、モチベーションやマインドセットなどの『ソフト面』での適合が不可欠になっている点です。以前は、戦略を実現するためには、スキルや能力がフィットする人材を調達すれば十分でした。マインドのマネジメントは、これまでのやり方で可能だったからです。しかし、現在は人材のダイバーシティや価値観の多様化により、過去のやり方ではうまく機能しないため、マインドセットやモチベーションを戦略的に適合させていくことが重要です。調達した人材にスキルがあってもモチベーションやエンゲージメントがなければ、戦略の実現は困難だからです」
そのうえで守島氏は「人材ポートフォリオ」とは、「戦略を実現する人材を確保するうえで、人材をいくつかの群(グループ)に分け、各々のグループの戦略実現との関連に基づいて、各グループの貢献の仕方や必要要件などを考え、人事管理の在り方を分けて考える方法」だと言う。
「人材ポートフォリオは『どのような人材が必要か』を定義するだけでは不十分です。その上で、雇用形態、評価、育成制度といった、マインドを含めた人事管理の仕組みまで構築する必要があります」
事業の特性によって最適な人事管理のあり方は異なるものの、最終的には戦略の実現に向けてどのような人材マネジメントを行うかを考えることこそが、人材ポートフォリオの基本だと守島氏は述べた。
守島氏による問題提起2:今後は雇用関係にない人材の確保が鍵を握る
これらの特性を踏まえ、守島氏は人材ポートフォリオの構築および変革が難しい理由として以下の二つを挙げた。
「一つ目は、戦略とリンクさせることの難しさです。高度な専門性を有する人材は企業戦略への貢献度が明確化しやすい一方、その他の人材は戦略実現への貢献が不明瞭なため、要件定義が困難となる傾向があります。
二つ目は、人材の質と量の把握が困難な点です。事業や戦略から、人材ポートフォリオを構築し、必要な人材を描き出せたとしても、現時点で要件を充足する人材が、数の面でも質の面でも社内に在籍しているのかを、正確に把握しきれない場合が多くあります。現在がわからなければ、未来への道筋は描けません」
さらに、日本特有の正社員に対する考え方が、計画的な人材確保を難しくしているという。
「日本では、正社員を『研究開発職』といった特定の職務で採用しても、一定の範囲内であれば人事異動によって全く異なる業務を任せることが当然とされています。例えば、研究開発職で入社した人や営業のトップが、人事部長になるケースも最近はよくみかけます。このように職務配置の自由度が高いと、会社の事業戦略上、『この分野に、このスキルを持つ人材が絶対に必要だ』という計画的な人材確保をしなくなってしまうのです。正社員で雇っておけば、後でどんな配置でも可能だという考え方をしてしまうのです」
ただ、守島氏は、アメリカでも、事業戦略と人材ポートフォリオを密接に連携できている企業は、決して多くないのが現状だと補足した。
最後に、守島氏は、人材ポートフォリオ構築にあたって注意すべき点として、今後は、雇用されない人材が増えることを強調した。
「特に今後、重要になるのがフリーランスや業務委託といった『雇用関係にない人材』の活躍。こうした人材をひきつけ、活躍してもらうのがカギになってきます。ただ、企業のパーパスに共感し、高いエンゲージメントを維持できるかが、人材定着と活用の鍵です。雇用されない関係で仕事をする人材が増えるなかで、そうした人材にも企業のパーパスを共有し、主体的に能力を発揮してもらえる環境を整えることが不可欠です」

冨樫氏の問題提起1:戦略の一貫性と人事側の体制を意識しなければならない
冨樫氏は、人材ポートフォリオの運用にあたっては、人事部門の体制をセットで考えることが不可欠だと説明した。人材ポートフォリオは戦略人事を実現するための手段であり、採用・育成・配置がチグハグにならないように一貫性を持たせることが前提となる。それらを運用する人事部門の体制が整備されていなければ、組織規模が大きくなるほど実効性の低下は避けられない。
「人事側の体制を整える際は、HRBPとの連携がポイントとなります。単一事業体や規模が小さい組織の場合は、体制が整っていない場合でも運用できるかもしれません。しかし一定以上の規模になると、人材ポートフォリオを戦略的に機能させるには、人事部門の体制整備が重要です」
冨樫氏の問題提起2:人材ポートフォリオ設計のポイントは「対象範囲」「切り口」「レベル」
続いて冨樫氏は、人材ポートフォリオを設計する際のポイントとして「対象範囲」「切り口」「レベル」の三つを挙げた。
「一つ目は『対象範囲』です。人材ポートフォリオは、必ずしも会社全体で描く必要はありません。複合事業体の場合、本社が担えるのは経営人材のポートフォリオ作りに限られてしまうため、事業別に戦略人事を行う必要が出てくるのは当然です。全社の人材をスコープにするのか、特定の事業、部門、領域を対象にするのかを、経営戦略と連動させながら決めることが重要です」
また、二つ目のポイントは「切り口/粒度」だという。人材の分類を、どのような切り口で、どの程度の粒度で設計するのか。今後注力していく「事業」「職種」などで分類するのが適切な場合もあれば、多様性が経営戦略上重要ということで「国籍」「性別」で分類するケースもあるかもしれない。特定の「スキル」や、経営志向・イノベーター志向などの「志向性」に着眼するケースも増えている。粒度という意味では、広く「IT/DX人材」という括りで管理するのが適している場合もあれば、より具体的にITのどのようなスキルを持った人材なのかを細かく分類すべき場合もある。事業戦略が実現されている状態が具体的に描けているほど、人材要件の設計も明確になる。
三つ目の「レベル」とは、DX人材レベル1、レベル2、レベル3、などのように、人材ポートフォリオ設計において必要となる人材タイプを特定するだけでなく、そのタイプにおける能力レベルまで砕いて設計し、管理するという視点である。ただしこの「レベル」について、冨樫氏は、「細かく設定することよりもまず決めて動き出すことが重要だ」と指摘する。
「『対象範囲』と『切り口』は軸を定めてから設計すべきです。しかし、『レベル』には正解がないため、明確に設定しようとしてもなかなか動き出せません。私がご支援してきた中で運用に成功している企業は、とにかくまず動き出し、違和感があればレベルを修正しながら進める、といったアプローチをしています」
さらに、人材ポートフォリオは設計して終わりではなく、運用段階においては、「現状と理想のギャップ」を埋めるために多様な打ち手が考えられる。
「採用やリスキリングなど幅広い打ち手があるため、画一的なものにとらわれる必要はありません。どの打ち手を使うのかよりも、『どのような人材をどのくらい確保したいのか』を明確にすることが大切です」
冨樫氏の問題提起3:明確なコンセプトは「To be」を決める重要な要素
企業の中には人材ポートフォリオ・マネジメントを統合報告書などで開示しているケースがある。それらの資料から、冨樫氏は人材ポートフォリオ・マネジメントに成功している企業の共通点を見いだした。
「各社で共通しているのは、現状からどのように変革を遂げるのかという勝ち筋、つまりコンセプトが明確になっている点です。コンセプトがない状態での人材ポートフォリオ設計は、目的を見失った作業になりがちです」
実際に、富士通では「『IT企業』から『DX企業』へ」、日立製作所では「『製品事業×国内中心』から、『サービス事業/グローバル』へ」、デンソーでは「『内燃機関・ハード中心』から『電動化・ソフトウェア・新領域中心』へ」、山陰合同銀行では「『金融機能中心』から『DX×コンサルティング』へ」といった変革のコンセプトが定まっている。
「自社の軸足を変えるためのコンセプトが明確になっていれば、そこに向けて必要な人材や行動の『To be』が具体的に設定できます。そのためにも、コンセプトを明確にすることが不可欠です」

グループディスカッション:人材ポートフォリオの設計・運用における取り組みと課題
続いて、参加者によるグループディスカッションが行われた。5グループに分かれ、「人材ポートフォリオの設計と運用で『手応えのある取り組み』と『直面している、または直面しそうな課題』」について議論。ディスカッション後は、各グループの代表者がディスカッション内容を発表した。
Aグループ

OMデジタルソリューションズ 本田氏:手応えのある取り組みとして、「経験」を可視化して議論を進めることが効果的だったという話がありました。一方、将来の戦略と人材ポートフォリオをひもづける妥当性を判断することが困難だという意見も挙がりました。ものづくりを行っている企業では、トップスキルを持っている人材の高齢化が進んでおり、その人たちの経験やノウハウを後世にわたって人材ポートフォリオに組み込んでいくことが難しいことも課題です。
Bグループ
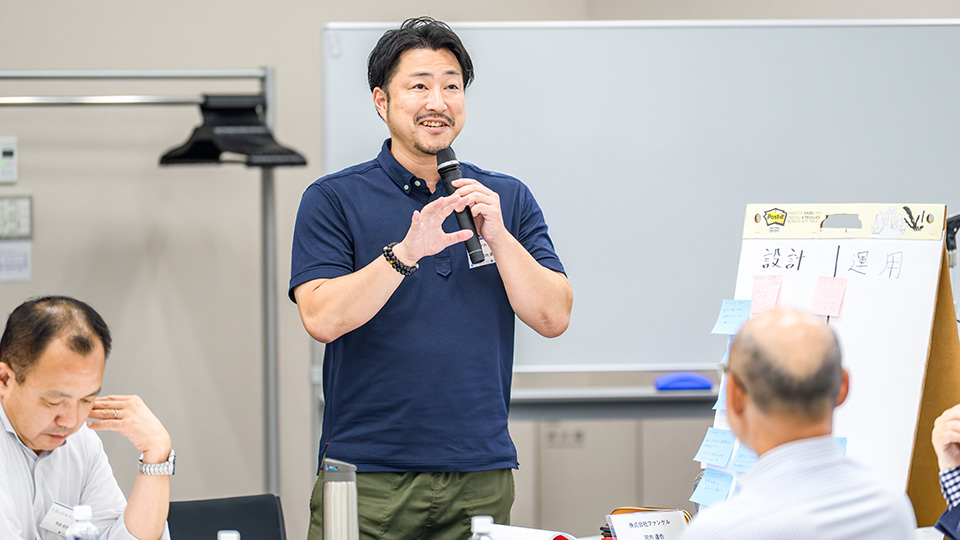
ファンケル 河内氏:経営人材に特化した領域では人材ポートフォリオが設計できているものの、それ以外の領域で大きく三つの課題が挙げられました。一つ目は、戦略を実現するために必要な人財像における「To be」の解像度が低いこと。二つ目は、「To Be」の解像度が高かったとしても今いる人財のスキルやモチベーションの可視化が難しいこと。三つ目は、可視化されたとしても戦略実現と人財の量・質の相関性の確からしさが担保できないため、人事部門側も事業部門側もコミットが難しくなり、なかなか運用が進められないことでした。
Cグループ

パナソニックインダストリー 岡田氏:人材ポートフォリオの前提となる企業戦略がまだ明確になっておらず、To-Beに関する議論がないまま人材ポートフォリオを設計しなければならないため、運用まで進められていないとのご意見がありました。また、実際に人材ポートフォリオを作ったものの、当てはめる人材をアセスメントすることが難しいというご意見もありました。
Dグループ

中村留精密工業 北村氏:課題としては、個人のスキルと組織のスキルを、どのようにセットしていくかを考えなくてはなりません。また、現場を巻き込まなければ人材ポートフォリオの運用は難しいので、その施策も検討していかなければならない、という声もありました。モチベーションなどのソフトスキルが重要だという話が参考になったので、今後は取り入れていきたいと感じました。
Eグループ

Hajimari 有賀氏:地頭と行動力の両軸でポートフォリオを組み、その両方が備わっている人材を中心に確保していく設計には一定の手応えを感じている、という声がありました。一方で、社内の役員が戦略に関して目線が合っていないことや、社外の業務委託も含めた人材ポートフォリオになっていないこと、部門別にあるべき人材像を考えたところ50個も案が出てしまったこと、戦略と結びつけるためのカテゴライズの方法が見いだせないことなどが課題として挙がりました。
冨樫氏・守島氏によるフィードバック
これらの発表を受けて、冨樫氏は「多くのグループでは、前提となる戦略の不明瞭さや人材ポートフォリオに落とし込む際の確からしさなどが課題として挙げられていました。たしかに戦略の具体性や、戦略と連動したあるべき人材ポートフォリオの妥当性は重要ですが、精緻にしようとし過ぎないことも重要です。ある一定のところで枝葉を切り落とし、人材戦略の幹がシンプルに伝わるような設計にする、という視点も、運用できてこそ意味があると考えるならば欠かせないものです」とまとめた。
守島氏は「人材ポートフォリオの構築は、最終的には、『アート』の側面を持つため、『競争力を維持するためにはこういった人材が必要なのでは』といったアバウトな前提で、まずは始めてもいいと考えています」と述べた。
「人材ポートフォリオの設計に科学のような正確性は求めにくいため、まずは動くことを重視し、正確性や完璧性にとらわれずに人材ポートフォリオの構築を始め、徐々に精緻にしていくことが重要になるのです」
全体ディスカッション:人材ポートフォリオの設計・運用で起きる課題に対する打ち手
次に、参加者全員と守島氏・冨樫氏が、人材ポートフォリオに関する「設計」「アセスメント」「現場の巻き込み・落とし込み」の三つの課題について、考えられる対応策を話し合った。
設計
アルプスアルパイン 小林氏:理想の人材ポートフォリオをいきなり設計することは難しいと感じています。人事部門が持っているデータからすぐに現場に反映できるのは「スキル」なので、スキルをベースに設計していくことが必要だと考えました。
冨樫氏:中長期のあるべき像(To Be)を具体的な人材ポートフォリオとして精緻に定めるのではなく、手元にある利用可能なデータを起点に増やすべき人材要件を定めていく、という考えですね。データが手元にある企業であれば、スピード、変化創出を重視するという意味では、十分に考えられる設計の仕方です。
リコージャパン 馬越氏:当社では、社内試験と公的資格によってスキルを可視化しています。ただし、スキルを有していても成果に結びつかなければ意味がないので、スキルと一定の成果と技能を掛け合わせて「プロ認定制度」として、プロレベルを判定しています。この制度によってある程度スキルの可視化はできているものの、戦略との結びつけに課題を感じています。
冨樫氏:人材ポートフォリオの設計で「To beの設計」と「As isの把握」が必要だと定義した際、「As isの把握」のために「プロ認定制度」という独自の人材要件・レベル設計をした、ということですね。
守島氏:人材ポートフォリオをスキルベースで考えるという声が多いようですが、それに疑問を感じる人はいますか。
サッポロビール 吉原氏:スキルの可視化は重要ですが、「As isの把握」にすぎません。「将来もこのスキルが必要なのか」という疑問が出てきます。
クレスコ 菊田氏:スキルを持っていても、周りの環境によってパフォーマンスは大きく変わります。スキルと環境を組み合わせて考えなければならないので、スキルだけを追っても思うような成果を得られません。
横河電機 河邊氏:マネジメントの階層によって可視化に求められるスキルの粒度は異なります。部課長レベルでは社員育成のためには具体的なスキル把握が必要となります。スキル管理に関してマネジメント階層に応じた粒度・可視化された情報の使い方を定義する必要があると感じています。
日本アクセス 西川氏:当社は全体的ではなく部分的に人材ポートフォリオを設計し、要件に合致する人材を「プロ人材」として採用しています。しかし、スキルベースで考えると戦略とマッチした人材ではなかったという経験もあります。そのため「自分たちの戦略においてどのような人材が必要なのか」を明確にする必要があると感じました。
アルプスアルパイン 小林氏:ハードスキルだけを見るのではなく、コンピテンシー、パーソナリティーや熱量といったソフトスキルまで把握することの大切さを感じています。
守島氏:日本の人事は「人を見る」傾向が強く、「その人は何ができるのか」「どういった経験を持っているのか」に関心があります。しかし、そうしたスキルはあくまでもツールでしかありません。大切なのは「ツールを使って何をするか、どういう成果を期待するのか」なので、スキルが明確になっても、使う目的が定まっていなければ宝の持ち腐れになってしまう可能性があります。
冨樫氏:守島先生がおっしゃるように「何をするか」は重要です。ところが、冒頭に話されたように、戦略が変わる速度が増している中、必要なスキルを全職種・階層で再定義し続けるのは非常に負担が大きい。そこで、会社があらかじめ定義したスキルを身につけさせるのではなく、必要なスキルが変わったら、自ら学び変化していくという「フューチャーレディネス」を人材要件のコアとして設定した事例もあります。先に議論されていたマインド面のひとつですね。
パナソニック インダストリー 岡田氏:この場でも、「スキル」という概念が幅広く捉えられているようです。そのため、専門的なスキルだけを指すのか、コンピテンシーも含めるのかといった共通認識を作ることが大事だと感じました。
アセスメント
守島氏:私はこの場では、シンプルに言えば「その人に何ができるか」「能力」のようなものを「スキル」と呼んでいます。しかし、世間一般では「マインドセット」「モチベーション」といったものも「スキル」と呼ぶ場合もあります。
冨樫氏:スキルは広義の概念なので、すべてを可視化するのは困難です。「TOEIC」や「ITパスポート」のような資格であればわかりやすいですが、ヒューマンスキルやコンセプチュアルスキル、リーダーシップ、マインドセットなどを精緻にレベル分けしたり、定量化して測ったりすることは容易ではありません。このアセスメントの在り方も、人材ポートフォリオの設計・運用においてしばしば課題となります。
リコージャパン 馬越氏:当社の「プロ認定制度」では、各職種に必要な技術や能力に基づき、多面評価でアセスメントを行っています。
Hajimari 有賀氏:社内でもアセスメントの意見がまとまらないケースがあります。そこで活躍している社員について、役員同士で話し合いながらグルーピングしています。今後はAIで仕組み化できないかと考えているところです。
冨樫氏:ヒューマンスキルやリーダーシップなどのアセスメントに関しては、マネジャー陣や外部アセッサーが直接判断するケースがよくあります。将来的にAIに判定を任せられる可能性もありますが、精度を求めるなら今は人が評価する領域がまだまだ多いと感じています。
守島氏:自社に必要なスキルをある程度決めたら、その要件に当てはまる人材がどこにいるのかを把握するため、最終的には人の目を通じて工数をかけて判断するべきだと考えます。
現場の巻き込み・落とし込み
冨樫氏:最後に、現場や経営層の巻き込みについてはいかがでしょうか。
ジール 長谷川氏:当社では年に一回、部長以上が集まって人材に関する課題を二日間討議する場を設けています。そこでは今期取り組むべき施策・テーマや、その実行方法などを考えています。
冨樫氏:現場の責任者が人材について定例で議論する場は、大切な取り組みです。昨今の人的資本経営の流れもあり、経営会議に人材戦略関連のアジェンダがセットされるようになったことで、経営層の巻き込みが難しいといった課題が減ったという声も聞いています。自社の人材課題について、経営層や部門のキーパーソンが真剣に向き合う定期的な場があるのは大きな意味を持ちます。
全体総括
最後に、冨樫氏と守島氏が以下のように総括した。
冨樫氏:人材ポートフォリオ・マネジメントを簡単にいうと、「経営戦略の実現のために必要な人材を増やし、不要な人材を減らすこと」です。この目的において「スキルの可視化」はあくまで手段のひとつですが、今日の議論の中では、そのアセスメント難度に悩まれている企業が多いと感じました。ITツールを活用することで、可視化の精度や効率は年々高まってはいますが、目的と手段が逆転し、「スキルの精緻な可視化」が目的になってしまわないように、自社が実現したいことを再点検していただければと思います。
守島氏:人材ポートフォリオの設計や運用にITを活用することは有効ですが、それだけでは不十分です。人による判断や、予測できない事態への対応といった「アート」の側面も同じように大切にしてください。人材に関する課題は複雑であり、最終的には「人」の判断が不可欠だからです。
また、その判断は、人事部門だけでなく現場のリーダーが行うことも重要です。これからの人事部門には、現場リーダーが主体的に人材マネジメントを行えるよう支援する「サポーター」としての役割が求められます。「現場が人材ポートフォリオを効果的に運用するためにどんな支援ができるか」を考えることが、人事部門の本来あるべき姿だと私は考えます。
ぜひ、この「アート」の重要性を社内で共有し、戦略を実現するために本当に必要な人材は誰なのかを、現場と共に考えていってください。
本セッションのまとめ
| 守島氏による問題提起 |
|
|---|---|
| 冨樫氏による問題提起 |
|
| グループディスカッション |
|
| 全体ディスカッション |
|
|
|
当日知見をご共有くださった皆さま
※所属や役職は「HRカンファレンス2025-夏-」開催時のものです。
有識者・プロフェッショナル
-
守島 基博氏
学習院大学 経済学部 経営学科 教授 / 一橋大学 名誉教授 -
冨樫 智昭氏
株式会社リンクアンドモチベーション 企画室 エグゼクティブディレクター
ご参加の大手・優良企業 (社名50音順)
- アルプスアルパイン(株)
- (株)インテージ
- auじぶん銀行(株)
- (株)エスシーシー
- (株)NTTデータMSE
- OMデジタルソリューションズ(株)
- (株)桐井製作所
- (株)クレスコ
- サッポロビール(株)
- (株)ジール
- (株)JR東日本情報システム
- 大日本印刷(株)
- 中村留精密工業(株)
- (株)日本アクセス
- (株)Hajimari
- パナソニック インダストリー(株)
- 日置電機(株)
- 日立建機(株)
- (株)ファンケル
- (株)三越伊勢丹ホールディングス
- 横河電機(株)
- リコージャパン(株)
経営学・社会システム論・行動経済学・心理学などの学術的背景を基盤にした、基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を用いた、組織や人事の経営コンサルティング。コンサルティング・クラウドサービスを通じて「診断」と「変革」のサイクルを提供することで、企業の「従業員エンゲージメント」向上をワンストップで支援。





