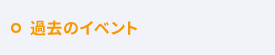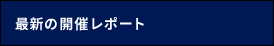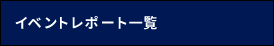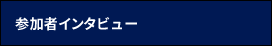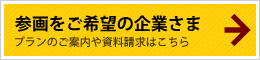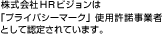苦境を乗り越え、集団・組織の「超回復力」を引き出すリーダーシップ
――いま求められる“レジリエント・リーダー”のすすめ――

金井 壽宏氏(かない・としひろ)
会社や職場が厳しい状況下にある時、明るく元気なリーダーはメンバーたちに活気を与え、場の雰囲気を盛り上げることができる。しかし、単に表面的な空気だけではなく、そのグループや組織が直面している危機的な場面、ハードな局面を、確実に乗り越えていけるように「メンバー全体を率いる力」を備えたリーダーこそが、今の時代では特に必要とされている。そんなリーダー像について、神戸大学社会科学系教育研究府長である金井壽宏氏は、「レジリエンス」という新しい概念を用いて語った。
逆境をくぐり抜けて、高い境地へと導くリーダーが必要
心理学において「レジリエンス」とは、「しなやかさ」や「弾力性」を意味する。また、大変な目に遭った時でも、ボキリと折れてしまうのはなく、きちんと元に戻す力を持つ人を「レジリエンス」な人と言う。金井氏は「レジリエント」なリーダー、すなわち「レジリエント・リーダー」を「回復型リーダー」と名付け、その象徴的な例を紹介した。
「映画『八甲田山』では、二つの連隊が別のルートで雪山を行軍します。共に厳しい道中ですが、一方の連隊のリーダーが『天は我々を見放した』という一言を口にした途端、その連隊はみんなバタバタと倒れてしまう。これは、上に立つ人が『なんとか回復するぞ』という気持ちを持たなかったら、その組織は終わってしまうことを表しています。折れそうになっても踏んばる姿は、個人の美徳としても大事ですが、部下を持つリーダーには、一層必要とされることだと思うのです」
逆境をくぐり抜けることで、以前の状態に回復させるだけではなく、前よりも一層高い境地へと導くこともある。そんな「超回復力」を引き出すリーダーの例を、金井氏は挙げた。
「たとえば、明治時代に岩倉具視たちが視察の旅に出ましたが、先進国の状況を見て『日本は遅れている』と悲観しないで、『日本はこういうふうに変われるんだ』と受け止めて帰国しました。だから、日本は進化したのだと思います。米国ではケネディが大統領に就任して『月に人が降り立つのを見たくないか』と発言したから、アポロ計画は進んだのです。リーダーシップ行動を考えると、誰もが実現は厳しいと感じるような絵をリーダーは描くものです。プロセスの中でうまくいかないことはあるはずですが、リーダー自身が必ず回復させるとか、あきらめないとか、そういう信念を持っていることが大事だと思います」
「緊張系」と「希望系」アプローチが必要
リーダー自身が信念を持てずに落ち込み、自分を鼓舞することもできずにいたとする。その時、たとえば「納期通りにできない」と心の中では思いながらも、部下たちに対しては「納期通りやろう」と宣言したところで、迫力に欠けるだろう。まずは、リーダー自身がやる気を自己調整できるようにならねばならない。そうすることで、リーダーは初めて部下にもやる気を与えることができ、さらには、部下一人ひとりがやる気を自己調整できるように育て上げることができるのである。
 「レジリエント・リーダーは、自身のやる気を高める術を心得ておくべきです。ある学説によると、人を動かすものは『このままでは目的が達成されない』という未達成感や心配や不安感にある。つまり、成し遂げていない目的を何とかしたいといった『緊張系』が心の中で働くために、実現へと向けたやる気が生じるのです。しかし、こういったネガティブとも言える『緊張系』な心理だけでは糸が切れてしまいます。『頑張れば何とかなる』『達成できそうだ』という、その先にある見通しや期待、すなわち『希望系』がペアになって人はうまく動いていくのです。この両面から、自身のやる気をコントロールできるようになって欲しいと思います」
「レジリエント・リーダーは、自身のやる気を高める術を心得ておくべきです。ある学説によると、人を動かすものは『このままでは目的が達成されない』という未達成感や心配や不安感にある。つまり、成し遂げていない目的を何とかしたいといった『緊張系』が心の中で働くために、実現へと向けたやる気が生じるのです。しかし、こういったネガティブとも言える『緊張系』な心理だけでは糸が切れてしまいます。『頑張れば何とかなる』『達成できそうだ』という、その先にある見通しや期待、すなわち『希望系』がペアになって人はうまく動いていくのです。この両面から、自身のやる気をコントロールできるようになって欲しいと思います」
ここで金井氏は、元ラグビー日本代表監督であり、現在もプロチームの総監督兼ゼネラルマネージャーである平尾誠二氏を紹介。不安(緊張)と希望を表裏一体のように巧みにコントロールしながらリーダーシップを実現してきた人物として、本人の言葉を引用した。
〈そもそも「こうなりたい」という願望や目指すべき理想を持たない人間が、不安を抱えたり絶望に陥ったりするのだろうか。自分の願いが現実のものにならない時、あるいは危機的な状況に陥りそうになったとき、人は不安や絶望を感じるのではないか。逆にいえば「こうなりたい」という気持ちがなければ、不安も絶望も感じるわけがない〉
「実は、人間は本来的に弱く、心配性であることがノーマルな状態だと言えます。『緊張系』と『希望系』では、より根本的なのは前者なのです。このことを、リーダーシップを発揮する行動に当てはめてみましょう。部下のやる気を高める時には、両面からアプローチしながらも『希望系』の発言を意識的に行うと効果が期待できることが分かります。たとえば『こういうことが実現したら、うれしいんじゃないかな』と声をかける。部下の持つ不安や心配を、払拭したり緩和させる方向へ働きかけるといい、というわけです」
リーダーとして心得るべき「関係系」「持論系」
部下のやる気、動機付けへのアプローチには「緊張系」と「希望系」の他に、「関係系」も挙げられる。人間は一人で生きているわけではなく、会社ではチームで仕事に取り組むことが多いからだ。たとえば、頑張り屋が周囲にいたり、あきらめずに粘る仲間を見ていれば、そこから何らかの影響を受けることは明らか。そういった人との関係性の重要さを示す資料として、金井氏は米国の心理学者エドガー・シャイン氏の著書の中の事例を紹介した。
「仕事の世界だけではなくて、家庭でも、趣味でも、人間は放っておくとすぐに課題面を前面に出してしまって、関係性がどうしても背後に退きがちになってしまうものです。シャイン氏は、ガン治療の専門医が、ガンを治すという課題一辺倒でなく、目の前にいる患者との関係に対する心遣いを常に見せていた治療プロセスを取り上げます。一番重要なポイントは、関係性を無視してタスク一筋でいくと、さまざまな問題が起こってしまうということだと書かれています」
 特に職場のように上下関係がある場合には、リーダーという指示をする側は命令形で発言しがちになる。すると、タスクに偏りギズギスした関係を招いてしまう。従って、リーダーは関係性を重んじて、謙虚な形で部下に質問するスタイルを心がけるべきだという。職場の関係性の中でも、リーダーの言動が部下を感化させる力が特に大きい事実について、金井氏は続ける。
特に職場のように上下関係がある場合には、リーダーという指示をする側は命令形で発言しがちになる。すると、タスクに偏りギズギスした関係を招いてしまう。従って、リーダーは関係性を重んじて、謙虚な形で部下に質問するスタイルを心がけるべきだという。職場の関係性の中でも、リーダーの言動が部下を感化させる力が特に大きい事実について、金井氏は続ける。
「名経営者は、自分なりの持論を持っています。大勢の人を引っ張ってきた経験に基づいて『こうやったら人が動く』というやり方です。各界のリーダーたちの著書も参考にしながら、リーダーが自身の『持論』を作りあげていき、部下に語るのは大切なこと。受けた薫陶をシェアしていくことにもなり、リーダーシップの連鎖という非常に重要な役割をも果たすのです。もちろん、部下たちは、簡単には諦めない姿勢や、うまくいかないことがあっても何とか変えようと立ち向かう姿も見ていますから、リーダー自身がレジリアントである姿を示すことは、新たに、粘り強い回復力を持つリーダーシップが生まれることにつながっていきます」
「修羅場経験」を振り返り、互いにシェアする効果
「修羅場経験」がリーダーシップを育てるということに、注目している学者たちがいるという。例えば、厳しい局面をくぐり抜けた経験を持つ人には、打たれ強さやしなやかさが加わるようになり、一皮むけて成長した姿をみせるようになる例は少なくない。修羅場経験を乗り越えた後に、回復力、超回復力を備えたリーダーが生まれるというわけである。
「関西の経済団体の中の人材育成に関する研究会で、“一皮むけた経験”に関する20人分のインタビューをまとめたことがあります。その中で、ヤマト運輸の社長を務めた瀬戸薫さんは、クール宅急便を始めるにあたってゼロから立ち上げたプロジェクトの大変さについて、話してくれました。お客様のニーズには確かな手応えを感じてはいたものの、温度管理の仕組みや運送工程などの中には分からないことが山積していたとか。しかし、瀬戸さんは『学んだことが非常に多かった』と振り返るのですね。修羅場経験は大変だけれど、同時に学びもある。そんな経営者やリーダーたちの修羅場体験談が次々と飛び出しました」
 個人個人が持つ修羅場経験の振り返りには大きな意義があるとして、金井氏は「イキイキチャート」を描いてみることを奨める。これまでの人生の中での自分のモチベーションのアップダウンを、キャリアの節目やプロジェクトの変化と共に時系列の曲線で描いてみるというものだ。チャートからは、人間の成長は一様ではなくてアップダウンを繰り返していることが分かる。また、ダウンした後に、ダウンする前よりも高い境地へとアップして超回復をみせているポイントも往往にして見られる。落ち込んでボキリと折れそうになる経験があったとしても、後から振り返ってみれば、それは自分の転換点となり成長に役立つポジティブな機会になっているという。
個人個人が持つ修羅場経験の振り返りには大きな意義があるとして、金井氏は「イキイキチャート」を描いてみることを奨める。これまでの人生の中での自分のモチベーションのアップダウンを、キャリアの節目やプロジェクトの変化と共に時系列の曲線で描いてみるというものだ。チャートからは、人間の成長は一様ではなくてアップダウンを繰り返していることが分かる。また、ダウンした後に、ダウンする前よりも高い境地へとアップして超回復をみせているポイントも往往にして見られる。落ち込んでボキリと折れそうになる経験があったとしても、後から振り返ってみれば、それは自分の転換点となり成長に役立つポジティブな機会になっているという。
「こういったことをレジリエント・リーダーの育成にぜひ活かしていただきたいと思います。例えば、社員の異動を考える時、あえて修羅場経験を持たせるような配属は、その人に回復力をつけたり、鍛えさせたりする機会を与えるといえます。経営幹部候補者の研修の中に、『一皮むけたいくつかの経験』をお互いにシェアするプログラムを組み込むことの効果は言うまでもありません。その場で語り合うだけではなくて、さらにドキュメント化してストックしておくとその価値は非常に増します。会社の経営幹部になる人たちがくぐり抜けてきた経験は、次の世代への重要なメッセージにもなります。このような回復・超回復力を持ったリーダーの存在は、もちろん、会社組織としての厳しい局面を打開する大きな力へと結びついていきます」
- お問合せ先
- 株式会社HRビジョン 日本の人事部
「HRカンファレンス」運営事務局 - 〒107-0062
東京都港区南青山2-2-3 ヒューリック青山外苑東通ビル6階 - E-mail:hrc@jinjibu.jp