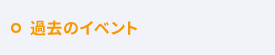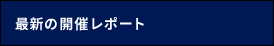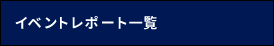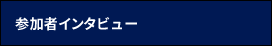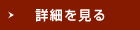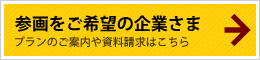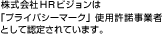パラダイムシフトするタレントマネジメント
~人財育成競争に勝つために~
(協賛:株式会社イー・コミュニケーションズ)

守島 基博氏(もりしま・もとひろ)
近年、日本企業の人材戦略において、「タレント・マネジメント」が一つのキーワードとなっている。実際、多くの企業によって実践されているが、一橋大学大学院商学研究科教授の守島基博氏は、「タレント・マネジメントについて考えることは、日本の人材マネジメントのあり方を根本から問い直すことになる」と語る。そこで今回は「パラダイムシフトするタレント・マネジメント ~人財育成競争に勝つために~」と題して講演を実施。「皆さんがいま行われていることは本当に正しいのか。それを考えるきっかけにしてほしい」という守島氏の講演からは、真のタレント・マネジメントの姿が見えてきた。
「こんなことはやってきた」程度の自覚では実践できない
守島氏の講演は、米国Society for Human Resource Managementによる、タレント・マネジメントの定義の紹介から始まった。
(SHRM、2006)
「皆さん、この定義の内容を理解できますか。わかりにくいでしょう。裏返せば、タレント・マネジメントとは誰も明確に定義できていない言葉なのです。また、この定義を読むと『こんなことはやってきたよ』と思われるかもしれません。しかし、それでは変革へと進んでいくことができない。一つ言えるのは、日本企業の人事はこれからかなり変わっていかなければ、グローバルなタレント・マネジメント競争や課題に対応できないということです」
守島氏は、今の日本企業に起きているのは「圧倒的な人材不足」だと言う。そして、人事が少しでも人材の不足を感じたなら、それはタレント・マネジメントの「失敗」だと語る。
 「日本企業は過去30年に、いろいろな変化を経験しました。グローバル競争、イノベーション、組織構造の変化も起きています。その結果何が起きたかと言うと、圧倒的な人材不足です。今、人材マネジメントはさまざまな経営課題に対して、本当に人材を供給できるかどうかが問われています。海外の一流企業は過去20年くらい、必要な人材をどうやって供給するかということに、本気で取り組んできました。それこそがタレント・マネジメントです。ただ、本当に供給しようと考えると、これまでの仕組みを劇的に変えなければいけない時もある。いま人事の皆さんがごく当たり前にやっている作業さえも、メスを入れなければいけないのです」
「日本企業は過去30年に、いろいろな変化を経験しました。グローバル競争、イノベーション、組織構造の変化も起きています。その結果何が起きたかと言うと、圧倒的な人材不足です。今、人材マネジメントはさまざまな経営課題に対して、本当に人材を供給できるかどうかが問われています。海外の一流企業は過去20年くらい、必要な人材をどうやって供給するかということに、本気で取り組んできました。それこそがタレント・マネジメントです。ただ、本当に供給しようと考えると、これまでの仕組みを劇的に変えなければいけない時もある。いま人事の皆さんがごく当たり前にやっている作業さえも、メスを入れなければいけないのです」
パラダイムシフトと最初に言い出したのはトマス・クーンという科学者。その意図は「当たり前のこと、その常識自体をなくしましょう」「個別ではなく全体を変えていきましょう」ということ。「私がイメージするのはかなりドラスティックです。がんばらないとできません。また、人事部門そのものも変わっていかなければならない。その両面があります」
たとえば、企業では「これからは新規事業だ、イノベーションだ」と叫ばれている。しかし、それを担う人材がいるかと言えば、人事も現場も「いない、足りない」と言う。「これはある意味、タレント・マネジメントが失敗しているということです。よく『社内にいないタイプを採用しなさい』などと言われますが、それがどこまで実行されているか。グローバル人材は、なぜ社内にいないのか。よく考えてみてください。コストなどの圧力に負けて、そういう人材を減らしてきたのではないですか。だからこそ、皆さんにはマインドセットの転換を行ってほしいのです。
さらなる問題は『隠れた人材コスト』です。人を充分に使い切れていないことによるコスト。その主な要因は、不活性人材と不適切配置人材です。優れた人材を充分に活用せず、そうでもない人材にポストを与えている。たとえば、皆さんの企業で年を取っているから、または昔貢献したからといった理由で、重要ポストに就いている人はいませんか。もしいるのだとしたら、ビジネスの観点から言えば明らかに間違いです。そして、そういう人がいると、若い人のモチベーションは上がらない。キャリアにも不安をもたらし、働きがいの喪失やバーンアウトにつながってしまう。これからの時代、そういう状態を放置したままで、本当にやっていけるでしょうか」
守島氏は「タレント・マネジメントは、誤解を恐れずに言えば、戦略に沿った人材の極限活用」と語る。それが一つの極意であり、そこにいるべきでない人がいれば外し、隠れた人材コストを減らして、活躍すべき人たちの能力を開花させる。
「いま大事なことは、ビジネスに必要な人材を、最大限に活用することです。そのためには、日本の人事が変わらなければいけない。社内でタレント・マネジメントを考えるべきなのは、他ならぬ人事だからです。これがパラダイムシフトの一つの大きなポイントだと思います」
人を分け、配置し、賭けて、リードし、活性化させる
これまでと違ったパラダイムでタレント・マネジメントを行うためには、具体的にどうすればいいのか。そこには五つのポイントがあると、守島氏は解説する。

社員を「優秀層」「普通の層」「対処が必要な層」に分けて扱い、別々にマネジメントを行う。「優秀層は放っておいても自分で育つと考える人がいるかもしれません。しかし、潜在力に投資して有効に使わないと、人材コストになってしまいます。また、タレント・マネジメントは優秀層だけに行えばいいと思っている人がいらっしゃいますが、普通の層とはっきり差を付けて双方に行うべきです」
適材適所は、人事の基本。守島氏は徹底して行うべきだと言う。「これまで言い訳をして、適材適所を行ってこなかったポジションはないでしょうか。海外のタレント・マネジメントの実例を聞くと、そのほとんどは適材適所の徹底がその基礎にあります。このことの重要性を認識してください」
人材の保有能力ではなく、潜在能力(≒伸びる力)を評価する。さらに、成長するかもしれない人材にはコミットし、投資をする。「日本企業では最近、成果主義の影響もあって、人の潜在性に賭けることが少なくなっています。成長するかもしれない人材にコミットしないのは、それだけで隠れたコストを高めているということです。ただし、抜てきしても期待に応えられないときは、降格させなければいけません。そのためには人事がきちんとデータを提供し、現場リーダーをサポートするのです」
企業経営とは「リーダーが人を集めてきて、事を成し遂げること」で、リーダーシップはその根幹となります。「現場で人を動かせるリーダーが数多い企業は、より多くのことを成し遂げられます。リーダーはビジネスをまとめて、達成までもっていく力があるからです」
現場の力を強くする。それでも、社員の2:6:2のうち、6である中間層の人たちをいかに活性化させるかは大切です。「無理やりではなく、普通にがんばれる状況をいかにつくるか。海外ではあまり中間層の人材についての議論はされませんが、日本の組織では、手当するべきタレント・マネジメントの対象です」
「こんな話を聞くと、『もうやってるよ』と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、問題はどこまで本気でやっているかです」と守島氏は語る。また、タレント・マネジメントは、優秀人材の引き留め(リテンション)マネジメントと言われるが、それは違うとも言う。「人事はリテンションよりも、いま社内にいる人が活性化することを大事に思うべきです。その対象に徹することが、タレント・マネジメントの基本なのです」
従業員に仕えながら、人と組織を開発する人事部へ
今後、真のタレント・マネジメントを行うには、人事自体のあり方も変わっていくべきだと守島氏は主張する。変革ポイントは以下の四つだ。

ドゥアブルは「自分ができること」であり、いわゆる日常業務や制度設計。内向きな志向。デリバラブルはその逆で「対象が外」にあり、そこにもたらされる価値を指す。まさに目的志向。「これからは徹底してデリバラブルであるべき。いま行っていることで何かがもたらされるどうかを考えてほしい。そして、結果を第一に考えること。『ビジネスパートナーとしての人事』を目指すべきです」
人事の主な顧客は、現場のリーダーと従業員。実際にビジネスを進める人を支援することが、人事の役目となる。「マーケティング志向と言ってもいいでしょう。顧客のニーズから考えるのです」
人事を、一つの施策ごとに考えるのでなく、束として総合的に考える。「人事戦略を立てるということと同じです。施策の組み合わせで思考します」
人を育て活用するだけでなく、組織そのものを強くすることを考える。「現場のリーダーが人材を育成するのですが、それをやりやすくする責任は、人事にあります。人事が人を育成できる組織をつくる。日本企業には組織開発部門があまり見られませんが、海外の企業では珍しくありません。それは、人をつくり込むことと同じくらい経営側が重要と思っているからです。この点は日本企業の弱点だと思います」
守島氏は、本来タレント・マネジメントの主体は現場のリーダーであるべきだが、日本の現場のリーダーにはその意識が弱いので、人事がその役割を担っていると語る。
「人事の皆さんには、タレント・マネジメントに本気で取り組んでほしい。そのために私は、これからも人事を変えていきたいと願う人たちのサポーターでありたいと思っています。皆さんのご活躍を期待しています。本日は、どうもありがとうございました」と守島氏は講演を締めくくった。
- お問合せ先
- 株式会社HRビジョン 日本の人事部 「HRカンファレンス」運営事務局
- 〒107-0062
東京都港区南青山2-2-3 ヒューリック青山外苑東通ビル6階 - TEL:03-5414-2219 E-mail:hrc@jinjibu.jp