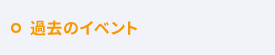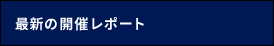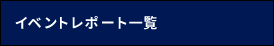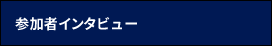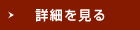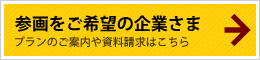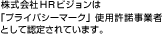グローバル人材戦略における【難題】
~アメリカ研修ビザ・日本ビザの活用法~
(協賛:一般社団法人 日本国際実務研修協会/行政書士法人IMS)

木滝 佳代氏(きたき・かよ)

川口 剛氏(かわぐち・つよし)
国際感覚を養うための海外研修、グローバル化に伴う現地駐在など、企業が社員を海外に派遣する機会が増えている。また、“海外からスペシャリストを採用する”“海外現地社員を国内に異動させる”といったように、外国人の国内採用を検討する企業も多い。しかし、その際に必要なビザの手続きが複雑なため、時間のロスが生じてしまっているケースが後を絶たない。グローバル人材戦略を円滑に進めていく上で最も取得困難なものの一つと言われる米国ビザ取得にについて、実務経験が豊富な木滝佳代氏、また日本ビザについては行政書士 川口剛氏が語った。
米国ビザは目的に応じて3種類から選択する
『J−1ビザ(米国交流訪問者ビザ)』は、米国国務省の認可を受け、ビザ取得に必要な適格証明書を発給する権限が、ビザスポンサーという米国機関に与えられている。日本国際実務研修協会(JIPT)は、そんなビザスポンサーの最大手Cultural Vistasとグローバルパートナー契約を結び、J-1研修ビザ取得のための一連の手続きと審査などの業務を幅広く担う。そのコンサルティングやオリエンテーションにも携わってきた木滝佳代氏が、まずは米国ビザの概要を紹介した。
 「米国に社員を90日以上の期間で派遣する際には、大きく3種類のビザがあります。商用目的なのか、就労目的なのか、研修目的なのか。渡米の目的に合致したビザを選択しなければなりません。〈商用目的〉は、販売、技術者の講演や研究、研修といった活動に従事する場合に該当します。ビザ取得者の報酬・給料は日本を源泉とすること、展示会等の出店等では日本製品の受注を主とすることなどが特徴に挙げられます。
「米国に社員を90日以上の期間で派遣する際には、大きく3種類のビザがあります。商用目的なのか、就労目的なのか、研修目的なのか。渡米の目的に合致したビザを選択しなければなりません。〈商用目的〉は、販売、技術者の講演や研究、研修といった活動に従事する場合に該当します。ビザ取得者の報酬・給料は日本を源泉とすること、展示会等の出店等では日本製品の受注を主とすることなどが特徴に挙げられます。
〈就労目的〉は、大きく三つあります。一つ目は、貿易投資・駐在員(E)ビザ。対アメリカに一定量の貿易実績をもつ、あるいは工場を立ち上げる企業のケースになどが該当します。英語能力は問われず、1回の取得での許可期間が長いのが特徴です。ただし派遣先の条件・派遣者の条件には細かな規定があり、派遣者は専門的な知識・経験を持つものでなければなりません。二つ目は、企業内転勤(L)ビザ。派遣者はある程度の業務経験年数のある管理職に相当するような方でなければなりません。また、米国の移民局の許可を得る必要もあります。三つ目は、特殊技能職(H-1b)ビザ。企業が選択するケースは少なく、大卒以上の専門職で一定の条件を満たす必要があります。
〈研修目的〉も、三つあります。一つ目は、座学・講習を中心とした研修向け(H-3)ビザ。二つ目は、短期の社内研修向け(B In Lieu of H-3)ビザで、米国源泉の報酬を受けないこと、生産的な作業・実務は認められないことが大きな特徴です。そして、三つ目が『J−1ビザ』と呼ばれる交流訪問者のビザ。トレーニング、インターンなどOJTを中心とした(Trainee / Intern)のカテゴリーを利用した研修です」
『J−1ビザ』のメリットと人材育成への活用例
『J−1ビザ』には税制面の優遇もある上、グローバル人材育成のプランニングに際して、活用しやすく高い効果が期待できる手段として、近年注目されている。メリットとしては、卒業大学、大学院の専攻と関連ある分野に従事している社員であれば、入社1年目からの申請が可能であることが第一に挙げられる。他の就労目的ビザに見られるような、キャリアや専門性を問う条件がないために活用範囲が広い。
「米国の受け入れ企業と日本の派遣元企業の間に、資本関係の有無を問わないという点も、他のビザと大きく違います。ご活用いただいている企業の中には、『取引先に研修に行ってみたい』『今後、業務提携を検討したい』と、派遣を検討されるケースも多く見受けられます」
また、米国の移民局を経由した手続きの必要がないために、通常は概ね数ヵ月程度は要する取得期間が短くて済むため、申請して1ヵ月から1ヵ月半後には渡米することも可能だと言う。「派遣期間は自由に設定できます。研修期間中の手当(給与)を、日米どちらの源泉にしても構わない点も大きなメリットです」
では、実際に『J−1ビザ』はどのように活用されているのか。『J−1ビザ』取得をサポートする日本唯一の団体としてストックされた事例を、ここでは紹介していった。「入社5年目ぐらいまでの社員を、子会社や関連会社に派遣して若手育成に役立てるケース」「将来の駐在員候補の見極めに導入するケース」「投資先や業務提携先を見極める目的で送り出すケース」「産学連携の一環として学生のインターンシップに採り入れるケース」など。最先端・最新の技術や、物流や会計など米国独自のシステムの習得を目指したケースは言うまでもない。OJTだけでなく研修時間外に語学研修を盛り込むケースもあるという。
「このように、『J−1ビザ』は他のビザに比べて、人材育成という観点からも非常に有効で汎用性が高いものです。文部科学省の国際教育交流担当職員長期研修プログラムを私どもで受託しており、ますます活用いただく機会が増えるのではないかと感じています。その他、米国国務省の助成金プログラムの取り扱い、個別のセミナー等もご要望に応じて承っています」
入国管理局の厳格な審査と罰則への注意
次に、外国人ビザに関する申請手続き約2万件という実績を持つ、行政書士法人IMSの川口剛氏が、日本の就労ビザ申請、外国人雇用に関する注意点を語った。観光客や3ヵ月以内の滞在者を除いた在留外国人数の推移は、近年ほぼ横ばいというデータがある。このような中長期滞在者が有する在留資格は、大きく三つに区分される。
 「“就労系”、留学生などの“非就労系”、日本人の配偶者などの“身分系”の三つです。日本に滞在するためには、活動内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。就労系で代表的な在留資格には、技術、研究、人文知識・国際業務、企業内転勤、投資・経営があります」
「“就労系”、留学生などの“非就労系”、日本人の配偶者などの“身分系”の三つです。日本に滞在するためには、活動内容に応じた在留資格を取得しなければなりません。就労系で代表的な在留資格には、技術、研究、人文知識・国際業務、企業内転勤、投資・経営があります」
一方、入国管理局が単純労働とみなす業務には、在留資格が存在しない。具体的には、一般事務、対面販売、レジ、洗い場、工場でのラインスタッフなどが挙げられる。就労資格は、日本人では適切な人材が得がたい職や専門性がある職に対して定められているため、それ以外は不許可となる可能性が高い。
不法滞在者の就労や、入国管理局に許可された活動範囲外の就労に対しては、外国人本人はもちろん、事業主も処罰の対象になる。不法就労者であると知らなかった場合であっても、採用時に在留カードを確認しなかった場合などは事業主の過失と見なされ、処罰は免れない。「知らなかった」では済まされないのである。
申請手続き上の注意と心得るべきポイント
申請手続き上の注意と心得るべきポイントについて、川口氏は次のように語った。「海外に在住する外国人を採用する場合、受け入れ企業や団体はまず、申請書や必要書類を作成し、本人から各種立証資料を取り寄せて申請することになります。入国管理局では、全てが書面審査です。口頭での説明や面談は基本的にないため、書類の選定や作成を誤ると、審査の遅延や不許可の可能性が高まります。
すでに来日している外国人の採用時には、主に2種類の申請が想定されます。一つは、現在従事している活動と異なる活動に従事する場合です。例えば、留学生が大学を卒業して就職するには、就労開始までに在留資格の変更許可申請を行い、許可を取得しなければなりません。もう一つは、転職や中途採用後の更新許可申請です。また、受け入れる企業や団体に対しても審査が行われます。“経営が健全で利益を出しているか”“ペーパーカンパニーではないか”といった企業の実態も審査され、特に中小企業の場合は、登記簿や決算書類の提出が義務付けられています」
 2012年5月に、海外の優秀な人材の受け入れを促進する「高度人材ポイント制度」が施行された。学歴、職歴、年収等を基準としたポイント制を通じて認定する新しい在留資格で、さまざまな優遇措置がある。なかでも、5年の在留期間の一律付与、永住申請時の要件緩和に対する反響が大きい。ただし、転職した場合の再申請の必要性等のデメリットを充分に考慮の上、総合的に判断し申請すべき、と川口氏は注意を促す。また、申請するか否かを判断するための情報収集の重要性は、この新制度に限ったことではないという。
2012年5月に、海外の優秀な人材の受け入れを促進する「高度人材ポイント制度」が施行された。学歴、職歴、年収等を基準としたポイント制を通じて認定する新しい在留資格で、さまざまな優遇措置がある。なかでも、5年の在留期間の一律付与、永住申請時の要件緩和に対する反響が大きい。ただし、転職した場合の再申請の必要性等のデメリットを充分に考慮の上、総合的に判断し申請すべき、と川口氏は注意を促す。また、申請するか否かを判断するための情報収集の重要性は、この新制度に限ったことではないという。
「入国管理局での審査基準や必要書類は常に変化し、かつ内容はその都度公開されず、いつの間にか必要書類が変更されていることが多々あります。そのため、入国管理局での日常的な情報収集は不可欠です。また、『以前は不要だった』『前回は何週間で許可が出た』『この前のケースでこうだった』という主張は一切通じません。必要書類や審査期間は完全にケースバイケースです」
外国人の採用、海外勤務の外国人社員の日本への異動、外国人留学生の雇用に際しては、書類の準備・作成時の負担が大きい点や、結果的に不許可となり採用や異動ができなくなるリスクも伴う。そんな時、ビザの専門家の力を借りれば、リスクを軽減・回避し、グローバル人材の採用手続きがスムーズに進む、と理解できた講演となった。
- お問合せ先
- 株式会社HRビジョン 日本の人事部
「HRカンファレンス」運営事務局 - 〒107-0062
東京都港区南青山2-2-3 ヒューリック青山外苑東通ビル6階 - E-mail:hrc@jinjibu.jp