新規事業を生み出す人と組織の育て方
人事に求められるイノベーティブな挑戦
田中 聡一さん(立教大学 経営学部 准教授)
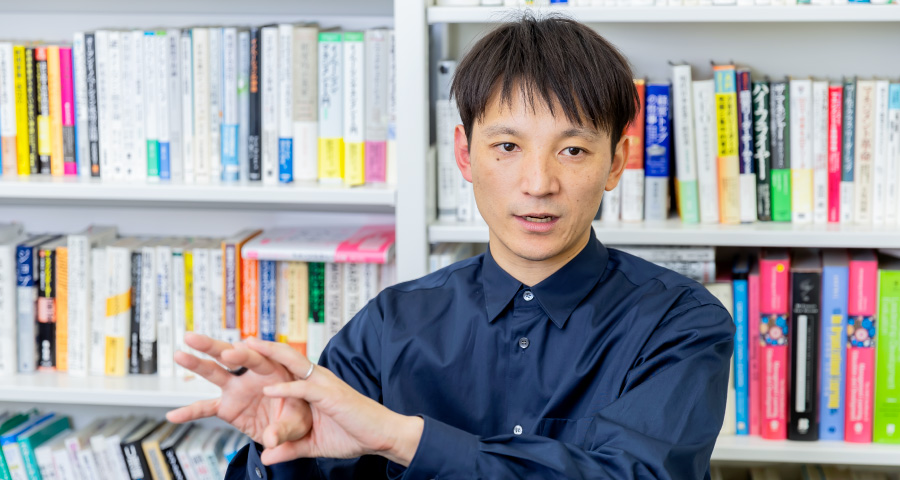
外部環境の急激な変化を受けて、企業には果断なイノベーションが求められています。一方で、新規事業の創出やイノベーティブな組織づくりに苦戦し、頭を悩ませている担当者も多いでしょう。立教大学の田中聡准教授は、「事業を創るには『創る人』『支える人』『育てる組織』の三位一体改革が必要」とし、経営者と人事にこそイノベーティブな挑戦が求められると言います。経営者や人事リーダーに求められる、エンパワーメントの取り組みを聞きました。
たなか・さとし/1983年 山口県生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。2018年より現職。専門は人的資源管理論・組織行動論・チームワーク論。主に経営人材の育成、新規事業部門の人材開発・組織開発などを研究している。著書に『経営人材育成論』(単著:東京大学出版会)『チームワーキング』(共著:日本能率協会マネジメントセンター)『シン・人事の大研究』(共著:ダイヤモンド社)など。
新規事業に本気になれない状態
多くの日本企業が新規事業創出に悩みを抱えています。
新規事業にまつわる日本企業の課題は、決して今に始まった話ではありませんが、ここ5年ほどで課題の「質」が大きく変わってきたと感じています。これまで新規事業といえば、事業戦略やファイナンスに関するテーマが主なアジェンダとして語られていました。
しかし、最近では「人と組織」に関する課題が表面化し、ますます重要になっています。新規事業の推進においては、単に戦略や資金を整えるだけでは十分ではなく、それを実行し、推進する「人」をどう見出し、育てるのか。そして、その「人」が力を発揮できるような「組織」のあり方、たとえば人事制度や組織構造、さらには組織風土をどうデザインするかが問われています。私が2018年に出版した『「事業を創る人」の大研究』では、「事業開発」と「人材開発・組織開発」を一体として考える重要性を指摘しました。当時は、事業開発は経営企画部の役割、人材開発・組織開発は人事部の役割といった管掌部門の違いから、二つのテーマがセットで議論されることはほとんどありませんでしたが、最近では多くの企業から「新規事業を創る人材をどのように発掘し育成すればよいのか」「新規事業を促進するための組織や風土をどう整備すればよいのか」といったテーマで相談を受ける機会が増えてきました。
具体的に「人と組織」からみた新規事業についてどのような課題があるのでしょうか。
具体的には、経営層、ミドル層、若手層それぞれに課題が存在し、それらが複雑に絡み合っています。
まずは経営層の課題です。大企業のトップの多くは任期制であり、長期的な視点で新規事業に取り組むインセンティブが働きにくい仕組みになっています。実際、10年以上の長期政権となるケースは珍しい。新規事業は短期間で成果を出せるものではありません。しかし、株主や機関投資家からの圧力もあり、多くの経営者は在任中に目に見える成果を求められるため、結果的に新規事業に対して本腰を入れて取り組めない状況が生じているのです。
次に、ミドル層についてですが、現在、管理職は「罰ゲーム」や「無理ゲー」とも形容されるように、膨大なタスクと重い責任を一手に引き受ける役割を担っています。部門の業績管理や多様化するチームのマネジメント、一人ひとりのメンバー育成や働き方改革への対応など、さまざまな課題に向き合っていて、ただでさえ忙しい。このような状況では、管理職が新しい挑戦に前向きになることが難しく、結果的に新規事業へのエネルギーやリソースが割かれにくい構造が生まれています。
最後に若手層の課題です。若手社員の多くは「新しいことに挑戦したい」という意欲を持っていますが、そのエネルギーが自社の新規事業に向きにくい現状があります。これは、若手が会社への帰属意識や貢献意欲を持ちにくい企業文化が影響しています。さらに、人材の流動化が進む中、個人のキャリア自律を優先する傾向が強まり、自社での長期的な挑戦よりも短期的な成果を求めがちです。
この続きは「日本の人事部 LEADERS(リーダーズ) Vol.13」でご覧になれます。
ご購入はこちら