2021年のHRコンソーシアム活動報告
概要
2021年も新型コロナウイルスの影響により、すべての分科会、全体交流会をオンラインで実施いたしました。
- <分科会(年8回開催)>
- 大手企業の人事エグゼクティブ、大学の研究者を講師として招聘。2021年は、スタンダードな講座に加え、特に課題意識の強い会員を対象にしたユニークなスタイルの講座を実施しました。
- ●2回連続講座
- 法政大学 坂爪洋美氏を講師にお迎えして、「管理職の役割」について2週連続の講座を実施しました。会後半には、オンライン上で参加者や坂爪氏が自由に意見を交わすまでに信頼関係が強化され、これまで以上にリアルな本音を語り合うことができました。
- ●6~12月インターバル講座
- 法政大学大学院 石山恒貴氏を講師にお迎えし、6月と12月に「新入社員育成」をテーマに講座を開講。半年間のインターバルを経て、各社の取り組みがどのように変化したのか、時系列で共有することができました。
- <全体交流会(年2回開催)>
- 2月5日は「レジリエンス」、9月3日は「パーパス」をテーマに、どちらも100人以上の人事担当者が参加いただきました。経営ビジョン推進に不可欠なトレンドワードということもあり、現場の担当者、リーダーはもとより、部長以上の役職者も多数ご参加いただきました。
| イベント | 時期 | 概要 |
|---|---|---|
| テーマ別分科会(前期) | 6月 | 「オンライン時代の新卒採用」・「ダイバーシティ・マネジメント(2回連続講義)」の2テーマで開催 |
| テーマ別分科会(後期) | 10月 | 「人材の配置・異動」・「ジョブ型雇用」・「オンボーディング」の3テーマで開催 |
| テーマ別分科会(通年) | 6月・12月 | 「新入社員育成」をテーマに開催。6月は問題意識や取り組み内容の共有、12月は取り組みの成果の共有を実施 |
| 全体交流会 | 2月5日 | オピニオンリーダー4名が登壇。人事に求められる「レジリエンス」についてディスカッション |
| 9月3日 | いまなぜ「パーパス」が必要なのか。オピニオンリーダー3名によるディスカッションで、パーパスの意義や重要性について議論 |
| イベント | 時期 | 概要 |
|---|---|---|
| HRカンファレンス | 5月・11月 | 合計12日間にわたる日本最大のHRイベント |
| HRアカデミー | 冬期:1~3月 夏期:6~9月 |
企業人事を講師に招いた講義。冬期・夏期各10回の年間20講座を開講 |
開催情報
人事限定 全体交流会(2021年9月開催)
- 全体交流会
-
講演テーマ 従業員がイキイキと働き、組織が活性化するために必要な「パーパス」とは
~企業は何のために存在し、人は何のために働くのかを考える~概要 新型コロナウイルス感染症の流行は、多くの企業にかつてないほどのインパクトを与えました。未だに今後の展開が見えない状況が続く中、多くの企業では、あらためて自社の「パーパス」について考える動きが活発化しています。パーパスが自社の指針となり、自分たちのあるべき姿、いま行うべき活動を示してくれるからです。それでは、企業はどのようにしてパーパスを定め、従業員と共有すればいいのでしょうか。また、パーパスによって従業員がイキイキと働き、組織が活性化するために、何をすればいいのでしょうか。富士通の平松氏、メルカリの木下氏がそれぞれの事例を紹介。慶應義塾大学の前野氏のファシリテーションで、パーパスの意義や重要性について議論します。視聴者の皆さまとの質疑応答、全員がグループに分かれてのディスカッションの時間も設けながら、いまなぜパーパスが必要なのかを明らかにしていきます。 講師/ファシリテーター 
-
平松 浩樹氏(ひらまつ ひろき)
富士通株式会社 執行役員常務CHRO■プロフィール
- 平松 浩樹氏(ひらまつ ひろき)
- 富士通株式会社 執行役員常務CHRO
- 1989年富士通株式会社に入社し、主に営業部門の人事を担当。2009年より、役員人事の担当部長として指名報酬委員会の立上げに参画。2015年より、営業部門の人事部長として働き方改革を推進。2018年より、人事本部人事部長として2020年4月に導入したジョブ型人事制度の企画・導入を主導。2021年4月より現職。

-
木下 達夫氏(きのした たつお)
株式会社メルカリ 執行役員 CHRO■プロフィール
- 木下 達夫氏(きのした たつお)
- 株式会社メルカリ 執行役員 CHRO
- P&Gジャパン人事部に入社し採用・HRBPを経験。2001年日本GEに入社、北米・タイ勤務後、プラスチックス事業部でブラックベルト・HRBP、2007年に金融部門の人事部長、アジア組織人材開発責任者を務めた。2011年に8ヵ月間のサバティカル休職取得。2012年よりGEジャパン人事部長。2015年にマレーシアに赴任し、アジア太平洋地域の組織人材開発、事業部人事責任者を務めた。2018年12月にメルカリに入社、執行役員CHROに就任。

-
前野 隆司氏(まえの たかし)
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授■プロフィール
- 前野 隆司氏(まえの たかし)
- 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授
- 慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長。ハーバード大学Visiting Professorなどを経て現職。博士(工学)。『幸福学×経営学』(2018年)、『幸せのメカニズム』(2014年)など多数。専門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーション教育など。
日時 2021年9月3日(金)14:00~16:00 対象 『日本の人事部』HRコンソーシアム会員、または優良企業人事部の皆さま 定員 100名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます参加費用 無料 会場 オンラインで実施



※2020年1月30日の全体交流会の様子
人事限定 全体交流会(2021年2月開催)
- 全体交流会
-
講演テーマ いま人事に求められる「レジリエンス」
困難や逆境を乗り越え、企業が発展していくために人事は何をすべきか概要 2020年の新型コロナウイルスの感染拡大は、経済活動に大きなダメージを与えました。企業に及ぼす影響も大きく、危機的状況を迎えた企業も数多くありました。人事の皆さんも、従業員の安全確保やリモートワークの推進、オンラインによる採用や研修など、大きな変化への対応に追われたことでしょう。今後はこの困難や逆境を乗り越え、いま一度企業を活性化し発展していかなければなりませんが、そのために人事は何をすべきなのでしょうか。神戸大学大学院の服部氏が、新型コロナウイルス関連の調査結果を発表するとともに問題提起。三人の人事リーダーが「レジリエンス」をテーマに議論します。視聴者の皆さまとの質疑応答、グループに分かれてのディスカッションの時間も設けて、いま人事に求められる「レジリエンス」について参加者全員で考えます。 講師/ファシリテーター 
-
佐々木 丈士氏(ささき たけし)
フェイスブックジャパン株式会社 人事統括 (Head of Human Resources)■プロフィール
- 佐々木 丈士氏(ささき たけし)
- フェイスブックジャパン株式会社 人事統括 (Head of Human Resources)
- フォード・ジャパン・リミテッド、フィリップ モリス ジャパンにおいて人事ビジネスパートナーとして様々な事業部門の組織開発を担当。2015年6月よりフェイスブックに入社、日本、韓国、パートナーシップ事業部の人事戦略を担当。

-
東 由紀氏(ひがし ゆき)
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 人事/総務本部 人事統括部 人財開発部 部長■プロフィール
- 東 由紀氏(ひがし ゆき)
- コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 人事/総務本部 人事統括部 人財開発部 部長
- ニューヨーク州立大学卒業後、外資系と日系の金融機関でセールスやマーケティングの業務に従事し、2013年に人事にキャリアチェンジ。野村證券でグローバル部門のタレントマネジメントとダイバーシティ&インクルージョンのジャパンヘッドに着任。その後、アクセンチュアを経て。2020年2月より現職で人財開発、採用、評価制度を統括。中央大学大学院戦略経営修士、職場におけるLGBTアライと施策の効果について研究。 2018年11月からAllies Connectの代表として、企業xアカデミックx社会のアライをつなげる活動を開始。特定NPO法人東京レインボープライド理事、認定NPO法人ReBit アドバイザー。

-
八代 茂裕氏(やしろ しげひろ)
株式会社湖池屋 経営管理本部 人事部 部長■プロフィール
- 八代 茂裕氏(やしろ しげひろ)
- 株式会社湖池屋 経営管理本部 人事部 部長
- 1981年、高卒でコマツに勤務しながら夜間大学にて学び、その後Sler、半導体メーカー、医療機器メーカーを経て2008年に湖池屋に入社。主に人事総務畑を歩むが、食品安全認証事務局なども経験し、2018年より人事部長。現在法政大学大学院にて人材開発を学ぶ。

-
服部 泰宏氏(はっとり やすひろ)
神戸大学大学院 経営学研究科 准教授■プロフィール
- 服部 泰宏氏(はっとり やすひろ)
- 神戸大学大学院 経営学研究科 准教授
- 1980年神奈川県生まれ。2009年神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了、博士(経営学)取得。滋賀大学経済学部情報管理学科専任講師、同准教授、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院准教授を経て、現職。日本企業における組織と個人の関わりあい(組織コミットメントや心理的契約)、経営学的な知識の普及の研究、シニア人材のマネジメント等、多数の研究活動に従事。著書『日本企業の心理的契約: 組織と従業員の見えざる約束』(白桃書房)は、第26回組織学会高宮賞を受賞した。2013年以降は人材の「採用」に関する科学的アプローチである「採用学」の確立に向けた「採用学プロジェクト」に従事、同プロジェクトのリーダーを務める。著書『採用学』(新潮社)は、「HRアワード2016」書籍部門最優秀賞を受賞。近著に『日本企業の採用革新』(中央経済社)、『組織行動論の考え方・使い方』(有斐閣)がある。
日時 2021年2月5日(金)14:00~16:00 対象 優良企業人事部の皆さま、または『日本の人事部』HRコンソーシアム会員 定員 100名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます参加費用 無料 会場 オンラインで実施
人事限定 テーマ別分科会(2021年6月・12月開催)
-
分科会 21-C 開催情報
-
テーマ <「HRコンソーシアム」オンライン 分科会>
法政大学大学院 石山氏と考える「新入社員育成」
2021年度の新入社員をどう育成し、戦力化していけばいいのか概要 2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、オンライン化への対応など、企業は新入社員育成の見直しを迫られました。2021年度、企業は新入社員育成にどのように取り組んでいけばいいのでしょうか。そして、その取り組みの成果を次年度以降にどうつなげていけばいいのでしょうか。本講座では、法政大学大学院 石山氏の問題提起を基に、参加企業同士による事例の共有やディスカッションを実施します。6月には問題意識や取り組み内容の共有、12月には取り組みの成果の共有を行う、全2回の連続講座です。 講師/ファシリテーター 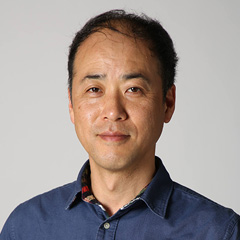
-
石山 恒貴氏(いしやま のぶたか)
法政大学大学院 政策創造研究科 教授■プロフィール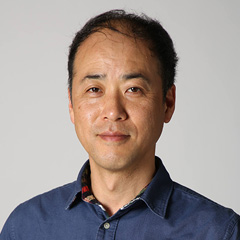
- 石山恒貴氏
- 法政大学大学院 政策創造研究科 教授
- (いしやま のぶたか)一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院経営情報学研究科修士課程修了、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了、博士(政策学)。一橋大学卒業後、NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。越境的学習、キャリア形成、人的資源管理等が研究領域。人材育成学会常任理事、日本労務学会理事、人事実践科学会議共同代表、NPO法人二枚目の名刺共同研究パートナー、フリーランス協会アドバイザリーボード。主な著書:『日本企業のタレントマネジメント』中央経済社、『地域とゆるくつながろう』静岡新聞社(編著)、『越境的学習のメカニズム』福村出版、2018年、『パラレルキャリアを始めよう!』ダイヤモンド社、2015年、『会社人生を後悔しない40代からの仕事術』(パーソル総研と共著)ダイヤモンド社、主な論文:Role of knowledge brokers in communities of practice in Japan, Journal of Knowledge Management, Vol.20,No.6,2016.
開催日時 第1回:2021年6月25日(金)18:00~20:00
第2回:2021年12月10日(金)18:00~20:00対象 HRコンソーシアム会員 定員 20名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
※1社2名様まで。開催場所 オンラインで実施
人事限定 テーマ別分科会(2021年10月開催)
-
分科会 21-D 開催情報
-
テーマ <「HRコンソーシアム」オンライン 分科会>
ブリヂストン 江上氏と考える「人材の配置・異動」
今、人事に求められる経営戦略と連動した人事戦略とは概要 ビジネス環境の変化が激しい現在、企業がさらに成長していくには、自社の経営戦略と連動した人事戦略の実行が不可欠です。そのために重要性が高まっているのが、人材の最適な「配置・異動」です。また、配置・異動させた人材を活躍に導くために、人事が果たすべき役割もこれまで以上に求められています。 本分科会では、複数の企業で人事責任者を務め、現在はブリヂストンにおいてテクノロジーを活用した人材マッチング施策を通じて適材・適所の実現に取り組む江上茂樹氏が登壇。江上氏からの事例紹介や問題提起を基に、参加者全員によるグループディスカッションや質疑応答を交えながら、これからの配置・異動のあり方について考えます。 講師/ファシリテーター 
-
江上 茂樹氏(えがみ しげき)
株式会社ブリヂストン
HRX推進・基盤人事統括部門長■プロフィール
- 江上 茂樹氏
- 株式会社ブリヂストン
HRX推進・基盤人事統括部門長 - (えがみ・しげき)1995年に東京大学経済学部卒業後、三菱自動車工業株式会社に入社し、川崎工場の人事・労務部門に配属。2003年のトラック・バス部門分社に伴い、三菱ふそうトラック・バス株式会社へ移籍し、人事・採用・教育を担当。CEOアシスタントや開発本部開発管理部長等を経て、2010年人事担当常務人事・総務本部長。独ダイムラー傘下となった同社の人事制度のグローバルスタンダードへの転換を図った。2015年11月サトーホールディングス株式会社に入社、執行役員最高人財責任者(CHRO)兼北上事業所長等を歴任し、海外を含めた人事制度の最適化や北上事業所の新建屋建設を推進した。2020年12月に株式会社ブリヂストンに入社し、人財マッチング企画・推進部門長を経て2021年9月よりHRX推進・基盤人事統括部門長。
開催日時 2021年10月8日(金)18:00~20:00 対象 HRコンソーシアム会員 定員 20名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
※1社2名様まで。開催場所 オンラインで実施
-
分科会 21-E 開催情報
-
テーマ <「HRコンソーシアム」オンライン 分科会>
いま、なぜ「ジョブ型雇用」なのか
注目される背景と導入を成功させるポイントについて考える概要 大手企業での導入が進むなど、現在大きな注目を集めている「ジョブ型雇用」。今後の導入を検討している企業も多いようですが、一方で「ジョブ型雇用に関して正しく認識できていない」「なぜ注目されているのか」という声も聞かれます。そこで本分科会では、雇用・労働経済を専門とする日本総合研究所の山田久氏が登壇。いまジョブ型雇用が注目される背景には何があるのか、どういった特徴があり、実際に導入するにはどうすればいいのかなどについて解説していただきます。参加者同士のグループディスカッションや質疑応答も交えながら、参加者全員でジョブ型雇用について考えます。 講師/ファシリテーター 
-
山田 久氏(やまだ ひさし)
株式会社日本総合研究所 副理事長■プロフィール
- 山田 久氏
- 株式会社日本総合研究所 副理事長
- (やまだ ひさし)京都大学経済学部卒業後、1987年住友銀行(現三井住友銀行)入行、1993年より日本総合研究所調査部。調査部長兼チーフエコノミストなどを経て2019年より現職。京都大学大学院博士後期課程修了、博士号取得。労働政策審議会・同一労働同一賃金部会委員などの公職を歴任。『賃上げ立国論』(日本経済新聞出版社、2020年)、『同一労働同一賃金の衝撃 「働き方改革」のカギを握る新ルール』(日本経済新聞出版社、2017年)など著書多数。法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科兼任講師。
開催日時 2021年10月15日(金)18:00~20:00 対象 HRコンソーシアム会員 定員 20名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
※1社2名様まで。開催場所 オンラインで実施
-
分科会 21-F 開催情報
-
テーマ <「HRコンソーシアム」オンライン 分科会>
甲南大学・尾形氏と考える これからの時代の「オンボーディング」
新卒・中途人材の組織適応と活躍に欠かせないサポートとは概要 どれだけ優秀な人材を採用できても、期待した成果を発揮し、組織に定着してもらえなければ意味がありません。そこで、新卒・中途を問わず重要になるのが、入社後の円滑な組織適応と早期活躍をサポートする「オンボーディング」です。人材の多様化が進む中、人事は新入社員や配属先にどのような支援をすればいいのでしょうか。また、オンラインでのオンボーディングにはどう対応していけばいいのでしょうか。 本分科会では、甲南大学 教授の尾形真実哉氏が、新卒・中途それぞれが組織に適応するうえでの課題やオンボーディングの基礎知識を解説。そのうえで、参加者同士で課題や事例を共有しながら、これからの時代に必要なオンボーディングについて議論します。 講師/ファシリテーター 
-
尾形 真実哉氏(おがた まみや)
甲南大学経営学部 教授■プロフィール
- 尾形真実哉氏
- 甲南大学経営学部 教授
- (おがた まみや)2004年神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士(経営学)取得。2007年甲南大学経営学部専任講師などを経て、2015年より現職。専門は組織行動論、経営組織論。著書に『若年就業者の組織適応: リアリティ・ショックからの成長』(白桃書房)、『中途採用人材を活かすマネジメント ―転職者の組織再適応を促進するために―』(生産性出版)。
開催日時 2021年10月22日(金)18:00~20:00 対象 HRコンソーシアム会員 定員 20名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
※1社2名様まで。開催場所 オンラインで実施
人事限定 テーマ別分科会(2021年6月開催)
-
分科会 21-A 開催情報
-
テーマ <「HRコンソーシアム」オンライン 分科会>
ソフトバンクの人事リーダー、実務担当者とともに考える オンライン時代の新卒採用概要 新型コロナウイルス感染症の流行で、2020年はオンラインで新卒採用活動を行う企業が増えました。この流れは今後も続くと考えられますが、オンラインで効果的な選考を行うために、人事はどう対応すればいいのでしょうか。本分科会では、ソフトバンクが取り組んでいる、AI面接や学生向けオンラインプログラムなどの事例を取り上げます。同社人事本部 本部長の源田氏が新卒採用の戦略や目標について、また、実務担当の中條氏が新卒採用での運用や実務に関する課題について共有。異なる視点から、新卒採用について考えます。参加者全員によるディスカッションも実施し、オンライン時代の新卒採用のあり方を明らかにしていきます。 講師/ファシリテーター 
-
源田 泰之氏(げんだ やすゆき)
ソフトバンク株式会社 人事本部 本部長
兼 未来人材推進室 室長
兼 組織人事統括部 統括部長■プロフィール
- 源田 泰之氏
- ソフトバンク株式会社 人事本部 本部長
兼 未来人材推進室 室長
兼 組織人事統括部 統括部長 - (げんだ やすゆき)1998年入社。営業を経験後、2008年より人事。ソフトバンクグループ社員向けの研修機関であるソフトバンクユニバーシティおよび後継者育成機関のソフトバンクアカデミア、新規事業提案制度(ソフトバンクイノベンチャー)の責任者。SBイノベンチャー・取締役を務める。孫正義が私財を投じ設立した、公益財団法人 孫正義育英財団の事務局長。孫正義育英財団では、高い志と異能を持つ若者が才能を開花できる環境を提供、未来を創る人材を支援。教育機関でのキャリア講義や人材育成の講演実績など多数。日本の人事部「HRアワード2019」企業人事部門 個人の部 最優秀賞 受賞。

-
中條 由唯氏(なかじょう ゆい)
ソフトバンク株式会社 人事本部 グループ人事統括室
グループ人材戦略部 グループ人材戦略1課■プロフィール
- 中條 由唯氏
- ソフトバンク株式会社 人事本部 グループ人事統括室
グループ人材戦略部 グループ人材戦略1課 - (なかじょう ゆい)2015年新卒入社以来、2021年3月まで新卒採用を担当。採用業務の中で、選考オペレーション全般・テクノロジー導入・就労型インターンの企画/運営・採用HPの制作等を担当。
開催日時 2021年6月4日(金)18:00~20:00 対象 HRコンソーシアム会員 定員 20名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
※1社2名様まで。開催場所 オンラインで実施
-
分科会 21-B 開催情報
-
テーマ <「HRコンソーシアム」オンライン 分科会>
法政大学 坂爪教授と考える これからの管理職の役割
社員のキャリア自律を促すダイバーシティ・マネジメントとは概要 社員一人ひとりが、自身の働き方や生き方を主体的に考えるキャリア自律が注目されています。自律的なキャリア形成を促すには、人事施策だけでなく、現場で社員と向き合う管理職からの働きかけも重要です。そこで求められるのが、個人の価値観を尊重し、多様な人材を生かして業務を遂行する「ダイバーシティ・マネジメント」。しかし、業務量や責任が増える中、管理職が求められる役割を果たせていないことも多いのではないでしょうか。 本会では、ダイバーシティ推進における管理職の役割に詳しい、法政大学 教授の坂爪洋美氏が、管理職が担うべきダイバーシティ・マネジメントについて解説。管理職が置かれている状況や、求められる役割の変化などを基に、多様な部下をマネジメントし、キャリア自律を促すにはどうすればいいのかを考えます。また、人事としてどんな支援ができるのかを、2回にわたりディスカッションします。 講師/ファシリテーター 
-
坂爪 洋美氏(さかづめ ひろみ)
法政大学 キャリアデザイン学部 教授■プロフィール
- 坂爪 洋美氏
- 法政大学 キャリアデザイン学部 教授
- (さかづめ ひろみ)人材ビジネス業に従事後、和光大学現代人間学部を経て、2015年4月より現職。2001年慶應義塾大学大学院経営管理研究科単位取得退学、博士(経営学)。専門は産業・組織心理学、人材マネジメント論。ダイバーシティの中でも、特に女性のキャリア形成ならびにワーク・ライフ・バランス推進における管理職の役割について研究を進める。近著に「シリーズダイバーシティ経営 管理職の役割」(共著、中央経済社)がある。
開催日時 第1回:2021年6月11日(金)18:00~20:00
第2回:2021年6月18日(金)18:00~20:00
※2回連続講座です。各回ごとにお申込みすることはできません。対象 HRコンソーシアム会員 定員 20名程度
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
※1社2名様まで。開催場所 オンラインで実施
