第1回 2026.01.14(水)16:00-18:00/ 人事制度改革 <受付終了しました>
NTTが挑む「脱・年功序列」の人事制度改革
専門性や自律的なキャリア形成支援に舵を切った狙いとは
NTTグループは年次・年功からの脱却とキャリア自律の促進を掲げ、大規模な人事制度改革を断行しました。その背景には、事業構造の変化に対する強い危機感があったといいます。管理職以外のキャリアの選択肢として「スペシャリストグレード」を新設するなど、社員の専門性を軸とした人事給与制度へ転換。意欲あふれる多様なグループ経営人材を輩出する取り組みとして“NTT University”を創設し、次世代の経営人材育成にも取り組んでいます。かつての日本的雇用の象徴ともいえるNTTグループを変革する取り組みは、どのように進められたのか。同社の事例から、これからの時代に求められる人事制度について考え、議論します。
●講師紹介

平井 光太郎氏
NTT株式会社 総務部門 人材戦略担当 統括部長
(ひらい こうたろう)1996年入社、ネットワークサービスの開発、計画、投資等を経験後、2023年から人材戦略担当へ異動。現在はNTTグループ全体の人材戦略、企業価値向上を目指し意欲あふれる経営人材を育成するプログラム「NTT University」を担当。
第2回 2026.01.22(木)16:00-18:00/ 管理職育成 <受付終了しました>
「管理型」から「支援型」へ――サッポロビールの「マネージャー修練プログラム」から考える、現代の管理職育成
サッポロビールは、2020年の人事制度変更を機に、マネージャーの役割を従来の「管理型」から「支援型」へと見直しました。メンバーの成長とエンゲージメント向上にはマネージャーの存在が不可欠であると再認識し、「メンバーを育てるスキル」への投資を本格化。「支援型マネージャー修練施策」を新たにスタートさせました。「マネージャーの最大の使命は人財育成である」を実現するために、マネージャー自身が学びなおす・学習する機会が必要と考え、マネージャーがアップデートすべきスキルとして「フィードバック」「リーダーシップ」などを定義。年間を通じた研修で、浸透を図っています。本講座では、サッポロビールの取り組み事例を学び、参加者との議論を通じて、これからの時代に求められる管理職育成の要諦について考えます。
●講師紹介

吉原 正通氏
サッポロビール株式会社 人事総務部長 兼 サッポロホールディングス株式会社 人事部長
(よしはら まさみち)大学卒業後、サッポロビールの人事部門からキャリアをスタート。給与計算システムの構築、人事制度改定、シェアードサービス会社の設立などを牽引。その後カナダ子会社にHR Managerとして駐在し、日本帰国後はM&Aに関わり、人事デューデリジェンス、子会社の統合などに携わる。その後自ら統合した子会社に出向し、ヨーロッパ海外飲料の輸入ブランドマネージャーを経験のち、サッポロビールに戻り人事制度を改定し、職務・役割要件制度、ノーレーティングなどを導入。その後サッポロ不動産開発人事総務部長を務め、2024年3月より現職。
第3回 2026.01.28(水)16:00-18:00/ 評価 <受付終了しました>
20年続く“全社員360度評価”
アイリスオーヤマを支える、社員を本気にさせる人事評価制度
アイリスオーヤマは「公正な評価の実現」を掲げ、社員一人ひとりの納得感を醸成しながら成長を促す組織づくりに注力しています。本講座では、社長を含む全社員が対象の「360度評価」や “気づき”を促す「イエローカード制度」、昇・降格をダイナミックに運用する「3車線人事」など、同社独自の評価・育成制度の詳細を解説。多角的でオープンな評価を通じて社員の主体的な成長を支援し、組織全体の競争力を高める戦略から、社員と組織を活性化させるヒントを探り議論します。
●講師紹介
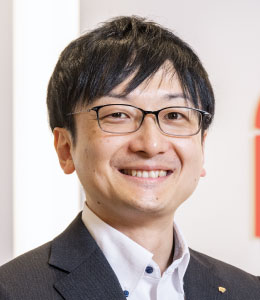
紺野 聡氏
アイリスオーヤマ株式会社 管理本部 人事部 部長
(こんの さとし)2007年に新卒でアイリスオーヤマに入社。ドラッグストアや家電量販店を中心に営業職として約10年従事。その後、商品開発・モノづくりを担う事業部で3年、営業管理本部で4年経験を積む。2024年より人事部に配属され、2025年1月より現職。営業から開発、管理、人事と多岐にわたる領域を経験し、現場と組織の両面に精通。
第4回 2026.02.04(水)16:00-18:00/ 戦略人事 <受付終了しました>
「戦略人事」をいかにして実現するのか
NOK 江上氏の持論・事例を基に考える、人事プロフェッショナルのあり方
「戦略人事」の重要性が叫ばれていますが、実現のためには人事リーダーだけでなく、人事部門のメンバー全員が「戦略人事」の発想やマインドセットを持って日々の業務に臨まなければなりません。本講座では、NOK株式会社でCHROを務める江上氏が、長年にわたりさまざまな企業で「戦略人事」を実践してきた上での持論と、現在NOKで取り組んでいる「戦略人事」の事例を紹介。人事という仕事の本質、人事プロフェッショナルのあり方を学んだ上で、「いかにして戦略人事を実現するのか」を参加者全員で考えます。
●講師紹介

江上 茂樹氏
NOK株式会社 執行役員 グループCHRO
(えがみ しげき)東京大学経済学部を卒業後、三菱自動車工業に入社。三菱ふそうトラック・バス転籍後は、開発管理部長や人事・総務本部長として外資系となった同社の変革に奔走。その後、サトーホールディングスならびにブリヂストンでCHROや人事・労務・総務責任者などを歴任。2024年1月よりNOKに参画し、24年7月より現職。
第5回 2026.02.18(水)16:00-18:00/ 育児支援
ピジョンに学ぶ、社員のキャリアと家族を支える「育児支援」の仕組みづくり
ピジョンは、育児を理由にキャリアを諦めることのない組織づくりに注力しています。本講座では、男性育休取得率100%を達成した道のりや、有志の社員が主体となった「社員で作り上げる育児制度プロジェクト」について解説。柔軟な働き方や、育休中の社員が開発に参加する独自の制度など、当事者のリアルな声から制度をアップデートした具体的な取り組みを紹介します。社員のキャリアと生活を支え、エンゲージメントを高める制度設計のヒントを探り、参加者とともに議論します。
●講師紹介

渡辺 雪香氏
ピジョン株式会社 経営戦略本部 人事部 人事労務グループ マネージャー
(わたなべ ゆきか)大学卒業後2004年にピジョンに入社し、以来労務(給与、勤怠、社会保険等)、採用・研修・ダイバーシティー・働き方改革・エンゲージメント向上・健康経営推進など、一貫して人事畑を歩む。2022年から現職。
第6回 2026.02.25(水)16:00-18:00/ AI人材育成
「事例化」をゴールに成果を出す
ダイハツ工業に学ぶ、ボトムアップ起点のAI人材育成戦略
AI人材育成に注力しているが実務成果に結びついていない、という企業は少なくありません。そこで注目されるのが、ダイハツ工業の取り組みです。同社では、有志によるボトムアップの活動を起点に、単なる知識習得ではなく、実務課題を解決する「事例化」をゴールとした全社的なAI人材育成を推進しています。本講座では、研修で学んだ知識を確実に業務成果へとつなげるためのプログラム設計と運用手法を解説。ボトムアップの熱意を全社的な変革に昇華させる秘訣(ひけつ)を学び、参加者同士で議論します。
●講師紹介

太古 無限氏
ダイハツ工業株式会社 DX推進室 デジタル変革グループ長 (兼) 東京LABOシニアデータサイエンティスト (兼) DX戦略担当
(たいこ むげん)2007年ダイハツ工業入社後は開発部にて小型車用エンジンの制御開発を担当。2020年から東京LABOデータサイエンスグループ長、2021年からDX推進室データサイエンスグループ長(兼務)を得て、DX推進室デジタル変革グループ長(兼)東京LABOシニアデータサイエンティストとして、全社のDX推進する業務に従事。その他に、滋賀大学データサイエンス部インダストリーアドバイザーとして、社外におけるAI活用の普及活動にも努める。経営学修士。
第7回 2026.03.04(水)16:00-18:00/ タレントマネジメント
「アジャイル型」人事データの整備・活用法
~アフラックの人財マネジメントに学ぶ~
人事には“経験や勘”も必要ですが、“データドリブン”な議論や意思決定を行うことも重要です。人的資本の情報開示の動きもあり、各社において、人的資本データの収集や活用は重要なテーマになっています。アフラック生命では、人的資本に関する定量データ(人的資本データ)の収集・分析・活用に力を入れており、経営レベルでの人的資本戦略のモニタリングから、現場のタレントマネジメントまで、幅広く人的資本データを活用する仕組みや体制を構築してきています。こうした取り組みを加速するために、2021年から人事部門に専門チームを立ち上げ、デジタルツールを活用した人的資本データの整備、ダッシュボード化を進めており、同時に、経営レベルでのガバナンス態勢の構築や、人的資本開示対応、ISO30414の取得などにもつなげています。自社の戦略に沿ったデータドリブンなタレントマネジメントを実現するためには、人的資本データをどのように整備・活用すればいいのか、アフラックの事例をもとに議論します。
●講師紹介

伊藤道博氏
アフラック生命保険株式会社 常務執行役員
(いとう みちひろ)1995年大卒後、アフラックに入社。人事部門に加え、支払査定、営業支社長など幅広い職務を経験。2019年アジャイル推進室の初代室長として全社変革をリード、2020年人事部長として人財マネジメント制度改革を実行。現在は人的資本戦略に加え、経営戦略等を担当。また、特例子会社のアフラック・ハートフル・サービス株式会社の代表取締役社長も兼務
第8回 2026.03.11(水)16:00-18:00/ ジョブ型人事制度
経営と現場、人事部門はいかにして人事制度を「共創」したのか
エイベックス流「ジョブ型人事制度」と「キャリア自律」
エンタテインメント業界をけん引するエイベックスは、経営ビジョン「avex vision 2027」の実現に向け、大規模な人事改革を実行しました。改革の核となったのは、約150もの職種を定義したジョブ型人事制度。全職種の職務要件・報酬体系の透明性を担保し、公募制度を導入することで、従業員のキャリア自律を強力に後押ししています。ポイントは、人事部門だけで決定するのではなく、各事業の責任者と膝詰めで議論し、制度を「共創」したこと。これにより、現場の納得感を高めることに成功しています。経営と現場、人事がどのように連携すれば、生きた制度を創り上げることができるのでしょうか。同社の事例を基に、これからの人事制度のあり方を議論します。
●講師紹介

小川 尚信氏
エイベックス・エンタテインメント株式会社 事業戦略本部 HRBPグループ ゼネラルマネージャー
(おがわ ひさのぶ)新卒でエイベックスに入社。営業を経験後、デジタル部門で音楽サブスクリプションサービスのローンチに携わる。2017年にCEO直下の新設部門でグループ全体の構造改革を推進し、人事制度設計や働き方改革、オフィスデザインなどを担当。現在は事業戦略本部で、人事全体の責任者とグループ各社のHRBP統括を担っている。
