変形労働時間制とは
労働基準法では、1日あたり8時間、1週あたり40時間という法定労働時間が通常定められています。そして、この基準を超えた分が残業時間という認定となります。
これに対して変形労働時間制とは、労働時間の合計単位を1日ずつではなく、月・年単位として計算するもので、職種によっては繁忙期等で勤務時間が増加した分を時間外労働という取り扱いにせず、閑散期等で調整することができるものです。
変形労働時間制は、労働者側からすると残業時間は一体どのくらいになっているのかが把握しにくいこともありますが、実は仕組みはシンプルです。
例えば、月金で9時~18時(休憩1時間)という勤務の職種もあれば、フライトアテンダントや大学教授の研究職など、決まった期間に仕事が集中せざるを得ない職種もあります。これら全てにおいて、同じ条件で労働時間を定めて残業代などの発生基準を設けることは難しいため、変形労働時間制というものが制定されています。
この変形労働時間制には、1ヶ月単位・1ヶ月超の期間もしくは1年単位で就労時間を設定する、という2種類があります。1ヶ月単位の変形労働時間制の採用にあたっては、28日間では160.0時間、29日間では165.7時間、30日間では171.4時間、31日間では177.1時間、という月ごとの法定労働時間以内に収めることが定められています。そして、この合計時間を各日と週毎というように振り分けていくわけです。
1年単位での変形労働時間制の採用にあたっては、その中でも1ヶ月以上1年未満という中で労働時間を振り分けていくことになります。まさに繁忙期・閑散期がある業務形態の企業での労働時間設定に適しています。365日間では2085.7時間、うるう年366日間では2091.4時間という法定労働時間になります。繁忙期に就業時間を多くしたり労働日数を週6にしたりなどの対応をし、その分を閑散期には就労時間や出勤日数を減らすことで休みを補い、年間就業時間合計を調整して年間法定労働時間内に収めるようにします。
1年単位というのはとても長い期間ですので、労働者を過労としないためにも休日の振り分け方はとても重要な項目となっています。そのため、1年あたり280日(労働日数)、休日85日(年間)、1日あたり10時間までの労働、1週間あたり52時間までの労働、連続労働日数は6日まで(原則)、特別な場合には最大連続労働日数は12日(1週間に1日休み)、という決まりが設けられています。
変形労働時間制の採用にあたっては、これらの決まりを踏まえて企業毎に就業時間を振り分けて定めることになります。
- 労務・賃金
- リスクマネジメント・情報管理
- 情報システム・IT関連
労務コンプライアンスで会社を守る方法をお教えします!
20年以上の経営者の経験と、いろいろな業務システムを構築してきた経験を活かして、会社を守るための勤怠管理システムとは何か?をお客さまと一緒になって考えていきます。
単にシステムを導入しただけでは、労働時間計算が楽になるだけです。
鈴木 孝裕(スズキ タカヒロ) 株式会社ウェブサーブ 代表取締役

| 対応エリア | 全国 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区 |
このプロフェッショナルのコラム(テーマ)
このプロフェッショナルの関連情報
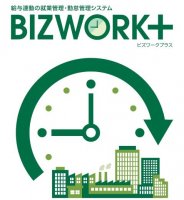
- お役立ちツール
- 就業規則・勤怠管理
- 労働時間制度
【解説】働き方改革関連法/時間外労働の上限規制①(厚労省)
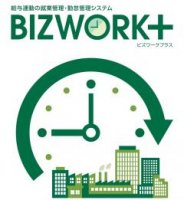
- お役立ちツール
- 給与計算・勤怠管理
- 導入コンサルティング






